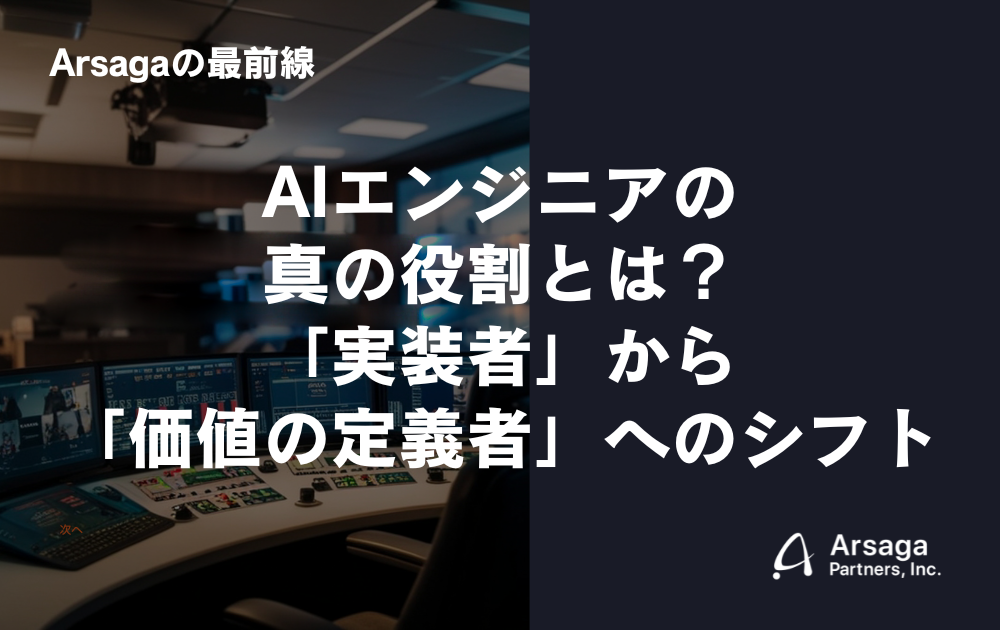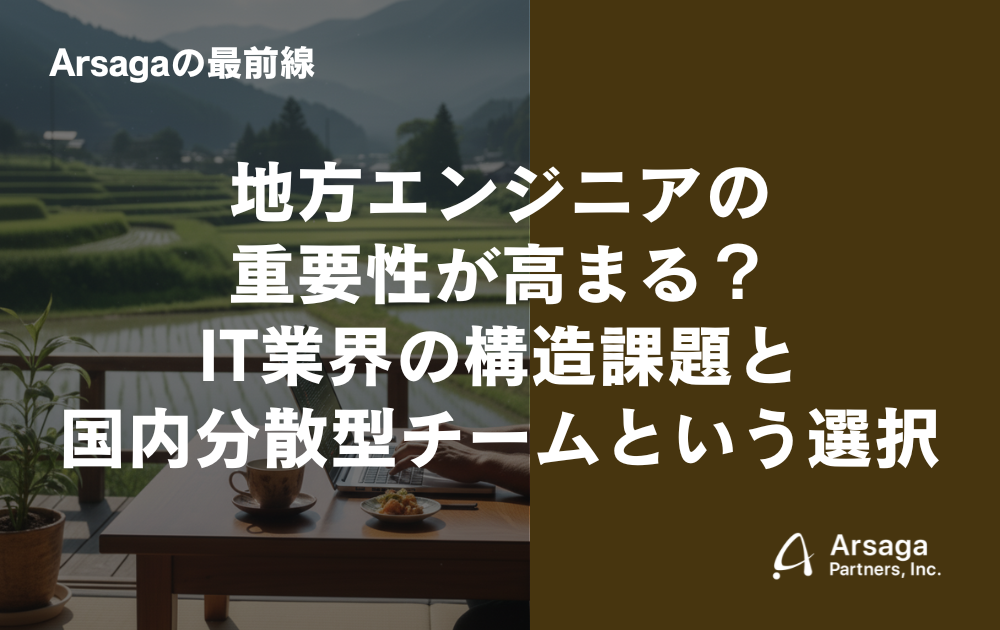機械学習の精度向上テクニック!初心者でもできる改善ステップとは?

機械学習モデルを作成していると思ったように「精度」が伸びず、つまずいてしまうことがあります。何度学習させても結果が改善されず、どこを見直すべきか分からなくなってしまう、そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、機械学習における「精度」の基本的な意味から、モデルのパフォーマンスを改善するための具体的な方法までを丁寧に解説していきます。専門的すぎる理論ではなく、実務や学習の現場で「すぐに役立つ」視点を意識してまとめています。これから精度向上に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
機械学習における「精度」とは何か

「精度」という言葉を聞くと、多くの人は「どれくらい正確に予測できているか」と直感的に考えるのではないでしょうか。ただ、機械学習の文脈で使われる「精度」は、もう少し明確な定義があります。
たとえば、分類問題における精度(Accuracy)は、「正しく分類できたデータの割合」を示します。計算式で表すと次のようになります。
精度 = 正解と一致した予測の数 ÷ 全体の予測数
一見すると非常にわかりやすい指標ですが、注意すべき点もあります。たとえば、全体の90%が「否」と答えるアンケートで、すべて「否」と予測すれば精度は90%になります。しかし、その予測は「はい」と答えた少数のケースをまったく見逃してしまっています。
このように、精度だけに注目すると、モデルの本当の性能が見えにくくなることがあるのです。
そこで役に立つのが「再現率」や「適合率」、「F1スコア」といった他の指標です。特に、クラスの分布が偏っている場合には、これらを併用して評価することが欠かせません。状況に応じてどの指標が重要かを見極めることが、最終的な「モデルの質」につながっていきます。
精度が伸び悩む原因を知る
モデルの精度が思うように上がらないとき、多くの方が「アルゴリズムが悪いのでは?」と考えがちです。でも、原因は必ずしもモデルそのものにあるとは限りません。いくつかの代表的な要因を見ていくことで、改善へのヒントが見えてくるかもしれません。
過学習と未学習のバランス
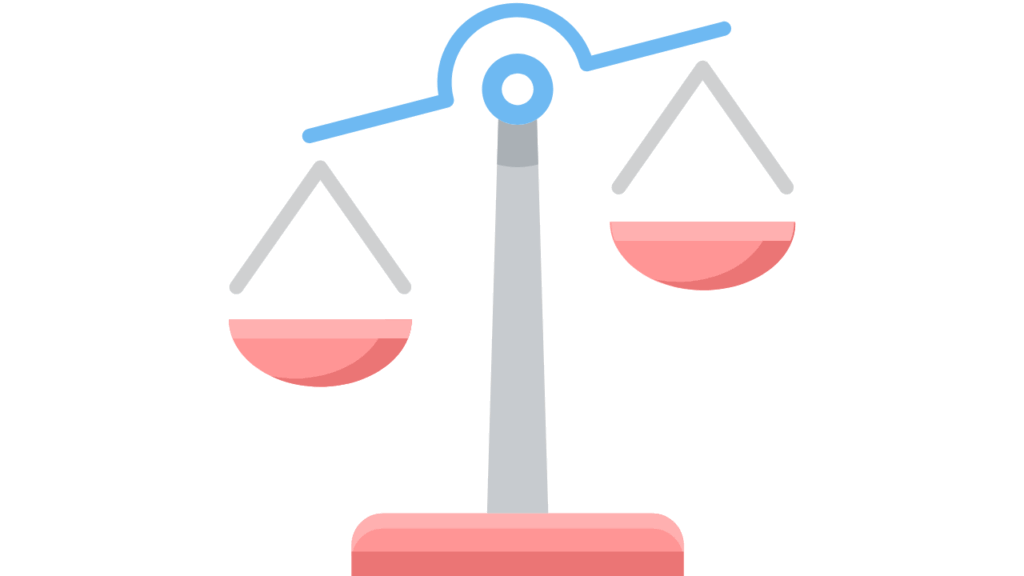
まず確認したいのが、「過学習」と「未学習」の状態です。
- 過学習(Overfitting):学習データに対しては非常に高い精度を出しているのに、新しいデータに弱い状態。モデルが細部にまで適応しすぎてしまい、汎用性を失っています。
- 未学習(Underfitting):そもそも学習データに対しても十分な精度が出ていない状態。モデルが問題の特徴を十分に捉えきれていません。
過学習か未学習かを見極めるには、訓練データと検証データの精度を比較するのが基本です。差が大きいなら過学習、どちらも低ければ未学習である可能性が高いでしょう。
データの質と量の問題
モデルの性能は、与えるデータに大きく左右されます。特に以下の点は、精度に直結します。
- ノイズの多さ:誤記や欠損が多いデータでは、モデルが正しい規則性を学ぶことができません。
- データ量の不足:特にディープラーニング系のモデルでは、数千~数万件のデータがないと性能が出にくい傾向があります。
- クラスの偏り:分類問題において、特定のクラスが多すぎると、少数派のクラスがうまく学習されず精度が下がります。
これらの問題は、単にモデルを変えるだけでは解決できないため、データそのものの見直しが必要になります。
モデルの選定ミスやハイパーパラメータの未調整
最後に注意したいのが、「選んだモデルやパラメータがタスクに適していない」ケースです。
たとえば、シンプルな線形モデルでは複雑な非線形関係を表現しきれないことがありますし、逆に深いニューラルネットワークを使っても、データが少なければ意味をなさないことも。
また、ハイパーパラメータ(学習率、木の深さ(*1)など)を適当に設定していると、モデルのポテンシャルを十分に引き出せないこともあります。モデル選定とチューニングは、セットで行うべき重要なステップなのです。
(*1)木の深さ:決定木などのツリーベースの機械学習モデルにおいて、ノードがどれだけ深く分岐していくかを示すハイパーパラメータ。この「木の深さ」を適切に設定しないと、モデルの性能を十分に引き出せないことがある。
精度を向上させるための基本アプローチ
モデルの精度を高めるためには、「これをやれば必ずうまくいく」という万能な方法はありません。しかし、多くの現場で実践されている“基本”ともいえる改善手法は存在します。まずは、その基本を押さえておきましょう。
特徴量エンジニアリングの工夫
最も大きな効果が期待できるのが、「特徴量(フィーチャー)」の見直しです。
機械学習モデルは、与えられた特徴量をもとに学習します。つまり、どんな特徴を与えるかによって、学習結果は大きく変わるということです。
たとえば、日付情報をそのまま使うのではなく、「曜日」や「月初かどうか」などに変換することで、モデルの理解が深まることがあります。また、数値同士を掛け合わせたり、対数を取ったりするなど、意味のある変換を加えることでも精度が向上することがあります。
このように、特徴量は「データの目利き力」が試される部分とも言えるでしょう。
適切なモデルの選択と比較
つい「とりあえずXGBoost(*2)で」となりがちですが、モデル選びは慎重に行いたいところです。
- 線形モデルは単純で速いけれど、複雑な関係性を捉えにくい
- 決定木やランダムフォレスト(*3)は非線形を扱えるが、過学習のリスクがある
- ニューラルネットワーク(*4)は強力だが、大量のデータと時間を必要とする
このように、それぞれにメリット・デメリットがあり、タスクやデータ構造によって「最適なモデル」は変わってきます。まずは複数のモデルを比較しながら、状況に合ったものを選ぶことが精度向上の第一歩です。
データ前処理の最適化
意外と見落とされがちなのが、データの「前処理」。これが甘いとどんなに高度なモデルでも力を発揮できません。
- 欠損値の処理(平均値補完、中央値補完など)
- カテゴリ変数のエンコーディング(One-Hot(*5)、Label Encoding(*6)など)
- スケーリング(標準化、正規化)
たとえば、スケーリングされていない数値が混在していると距離ベースのアルゴリズム(サポートベクターマシン/SVMやk近傍法/KNNなど)は誤った判断をしてしまいます。前処理は“見えない地盤づくり”のようなものであり、ここを丁寧に行うだけで精度が一段階上がることもあります。
(*2)XGBoost:機械学習の手法のひとつで、複数の「決定木(Yes/Noの判断の集まり)」を順番に組み合わせて予測精度を高めるアルゴリズム。
(*3)ランダムフォレスト:たくさんの弱い予測を組み合わせて、より正確で安定した予測をする方法
(*4)ニューラルネットワーク:複雑なパターンや関係を学習して予測する、脳の神経回路を模したアルゴリズム
(*5)One-Hot:カテゴリデータを機械学習で扱えるように数値化する方法
(*6)Label Encoding:カテゴリデータを整数のラベルに置き換える方法
ハイパーパラメータチューニングの重要性
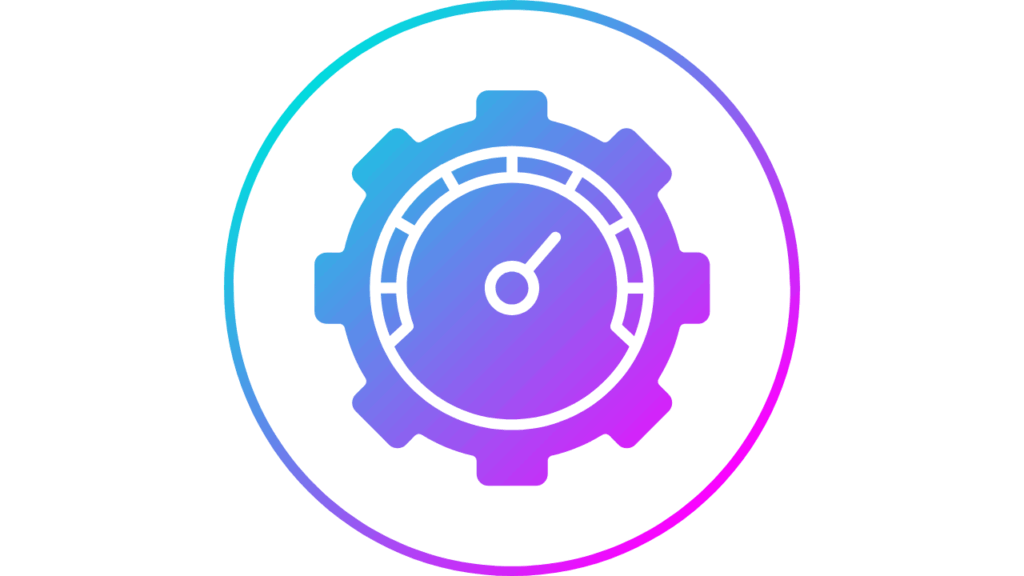
モデルを構築したあと、つい満足してしまいがちなのが「ハイパーパラメータの調整」です。しかし、このステップを丁寧に行うかどうかで最終的な精度には大きな差が出ます。
ハイパーパラメータとは、モデルの学習方法を左右する設定項目のようなもの。学習率や木の深さ、正則化の強さなどがそれに当たります。モデルの挙動をコントロールするレバーのような存在と言えるでしょう。
グリッドサーチとランダムサーチ
調整方法としてよく知られているのが、「グリッドサーチ」と「ランダムサーチ」です。
- グリッドサーチ:あらかじめ決めた複数のパラメータの組み合わせをすべて試す方法。手間はかかりますが、丁寧に探れば最適解に近づけます。
- ランダムサーチ:ランダムにパラメータを選んで試す方法。計算コストを抑えつつ、ある程度の精度向上を狙いたいときに有効です。
特に計算資源が限られている場合は、まずランダムサーチでざっくりと傾向をつかみ、その後グリッドサーチで絞り込むというステップも有効です。
ベイズ最適化の導入
さらに精度を追求する場面では、「ベイズ最適化」と呼ばれる方法を取り入れるケースも増えています。
これは、「試行錯誤の履歴」をもとに次に試すべきパラメータを予測してくれる仕組みです。機械学習モデル自身がチューニング作業を“効率よく進めてくれる”とも言えます。
具体的には、「Optuna」や「Hyperopt」などのライブラリを使えば、比較的簡単にベイズ最適化を実装できます。特にパラメータ数が多い複雑なモデルでは、その効果を実感しやすいでしょう。
チューニングは「時間をかける価値がある」工程
多くの人がモデルを作って終わりにしがちですが、本当の勝負はこのチューニングにあります。ある程度モデルが形になったら、パラメータの調整に時間を割いてみてください。それだけで精度がさらに上がることも、珍しくありません。
実務でも使われる精度改善のテクニック
実務の現場では、モデルの精度を上げるために経験的に効果があるとされるさまざまなテクニックが使われています。こうした方法は、理論的な正しさに加え、再現性や安定性を重視しているのが特徴です。ここでは、現場でよく使われている3つの代表的な手法を紹介します。
クロスバリデーションで安定性を確保

データを訓練用と検証用に分けるとき、たまたま偏ったデータが検証に入ってしまうと、精度が不安定になります。これを防ぐために有効なのが「クロスバリデーション」です。
代表的なのは「k分割交差検証」です。これは、データをk個のグループに分けて、1つを検証用に、残りを訓練用にして学習を行い、それをk回繰り返して平均精度を出す方法です。
この手法を使うことで、「どのデータに対しても安定した予測ができるモデルかどうか」がわかり、モデルの信頼性を高めることができます。
アンサンブル学習で「弱点」を補い合う
一つのモデルだけで高い精度を出すのが難しい場合、複数のモデルを組み合わせる「アンサンブル学習」が有効です。
- バギング(例:ランダムフォレスト):同じモデルを複数作り、それぞれ違うデータで学習させて平均を取る方法。ばらつきを抑えるのに向いています。
- ブースティング(例:XGBoost、LightGBM):前のモデルのミスを次のモデルが学習していくスタイル。予測の精度を少しずつ高めることができます。
アンサンブルを使うことで、「個々の弱点を全体で補い合う」ような形になり、結果として高精度な予測が得られることが多いのです。
データ拡張と外れ値処理の工夫
最後に触れておきたいのが、「データ自体を調整する」アプローチです。
- データ拡張(Augmentation):画像やテキストでは、元のデータを加工してデータ量を増やすことで、学習の質を高めます。たとえば画像を回転させたり、明るさを変えたりするなどの手法があります。
- 外れ値処理:極端に異なる値が学習を妨げることがあるため、外れ値を除外したり、ロバストな手法で処理したりすることで、精度の安定につながります。
これらの処理は、モデルを変更せずとも、データからの学びやすさを改善する方法として、非常に重要です。
精度向上のために意識しておきたい考え方
ここまで、モデルの精度を高めるための具体的な手法を紹介してきました。ただし、どれだけ技術的な工夫を重ねても、それが「本質的な改善」につながらないこともあります。
そこで大切になるのが、精度向上に取り組む際の考え方です。少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、実務においてはむしろこの視点こそが重要になることがあります。
精度だけでなく、汎化性能を意識する
目の前の数字に一喜一憂してしまいがちですが、本当に求めるべきは「新しいデータに対しても安定して予測できる力=汎化性能」です。
テストデータで高い精度が出ていても、それがたまたま似たようなパターンに偏っていた場合、現実の場面ではうまくいかないことがあります。精度を追い求めるだけではなく、「このモデルはどの程度汎用的に通用するのか?」という視点を持っておくことが、より本質的な改善につながります。
検証データの正しい使い方を守る
精度を上げることに夢中になると、知らず知らずのうちに検証データまで“学習の一部”のように扱ってしまうことがあります。特に、特徴量の工夫やハイパーパラメータの調整を繰り返していると、「検証データに最適化されたモデル」になってしまいがちです。
この状態は一種の情報漏洩(データリーク)と呼ばれ、本来なら見えないはずの情報に依存して精度が上がっている状態です。こうなると、実際の運用ではまったく使い物にならないモデルになってしまうことも。
検証用データはあくまでも“学習とは切り離した評価専用のデータ”と位置づけ、一度使ったら固定する・最終評価用のデータは別に取っておくといった工夫が必要です。
評価指標は「課題に即して」選ぶ
そして最後に意識したいのが、「精度=Accuracy」が常に最適な評価指標ではないということです。
たとえば、医療診断のように「見逃してはいけない」ケースでは、再現率(Recall)が重視されますし、不正検知など「誤検出を減らしたい」場面では、適合率(Precision)が重要になることもあります。
つまり、どんな精度を高めるのかは、「何を最も重視するべき課題なのか」によって変わってくるということです。現実的な課題に即した指標を選ぶことで、モデルが本当に解決すべきことに向き合えるようになります。
まとめ
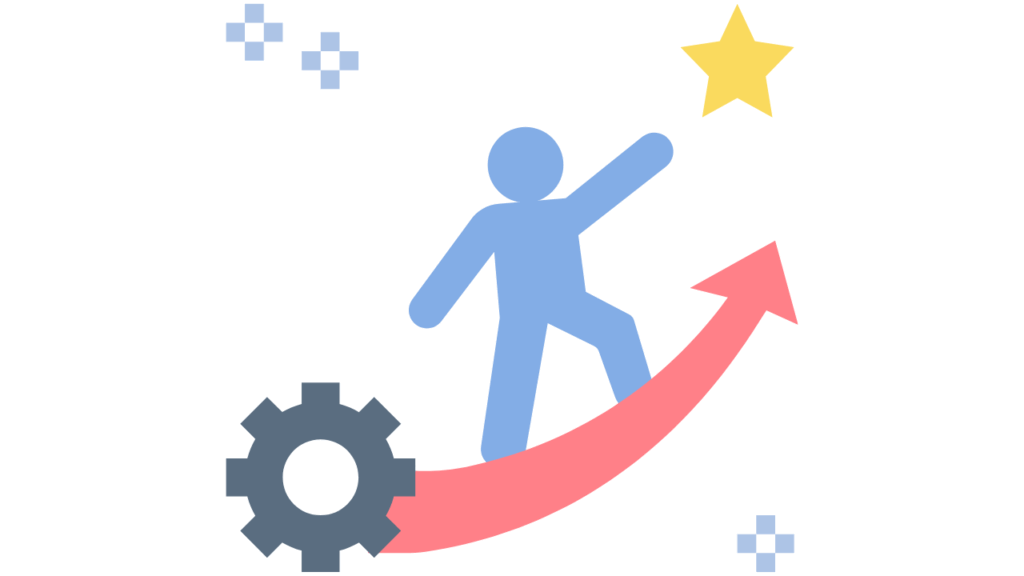
モデルの精度を高めるには、技術的な工夫だけでなく、「何を目指すべきか」という視点も欠かせません。特徴量の工夫やハイパーパラメータ調整などの定番手法に加えて、データの扱い方や評価方法を正しく理解し、常に現実に役立つモデルを目指していくことが最終的な成功につながっていきます。
合わせて読みたい記事:
生成AIが変えるプログラミング。初心者からプロまで知るべき動向
(文=広報室 白石)