第17回アルサーガLTイベント「Taste of Tech」レポート

2025年9月11日(木)、アルサーガパートナーズ(以下、アルサーガ)では社内向けライトニングトークイベント「Taste of Tech(通称TOT)」を開催しました。
今回のTOTには、東京本社からエンジニア&コンサルタントの4名が登壇。技術の話はもちろんのこと、現在興味のあるサービスや、弊社内でも大注目のテーマについても語ってくれました。
それでは、第17回TOTのイベントレポートをお届けします!
「Taste of Tech」とは
「Taste of Tech」(通称TOT)は、「ゆる〜くTechを楽しむこと」をコンセプトに、みんなの「知っている」「知りたい」を他のメンバーにお裾分けするための社内LT(ライトニングトーク)イベントです。 内容はTechに限らず、技術者やビジネスマンなど様々なバックグラウンドを持った人が登壇し、それぞれが培った知識や経験を共有する場となっています。
TOTの目的
• アウトプットの機会をつくりたい
• 社内にナレッジを貯められる場をつくりたい
• コミュニケーションの場をつくりたい
• メンバーの交流を深めて多様性をつくりたい
第17回TOTの様子
今回は以下の4名に登壇してもらいました。
▼1人目:田代さん(サーバーサイドエンジニア)
「最近話題のサービス3選」

トップバッターの田代さんは、個人的に「話題でアツい」と感じているWebサービスを3つ紹介してくれました。
最初に紹介されたのは、駐車スペースのシェアリングサービス「akippa(アキッパ)」。個人の空いている駐車場や自宅の敷地を15分単位で貸し出せるサービスで、スマホアプリに登録するだけで誰でも駐車場のオーナーになれる手軽さが特徴です。
ユーザーはアプリで予約すれば確実に駐車場を確保できるため、特にイベント会場周辺などで駐車場が空いていなくて困る!ということがないため、とても便利だと語ってくれました。
次に紹介されたのは、定額制で全国約270拠点のシェアハウスに住み放題のサービス「ADDress」。月額9,800円からのプランもあり、ワーケーションや「トライアル移住」にも気軽に活用できる点が魅力的です。私自身も知っているサービスでしたが、改めて使ってみたいと感じました!
最後に、世界中の新しいプロダクトが毎日投稿されるプラットフォーム「Product Hunt」を紹介。開発者に直接質問や意見交換ができるコミュニティ機能が特徴で、新しいサービスのUI/UXからヒントを得るなど、業務に活かせる点も多いとのことです。
普段自分ではなかなかキャッチしきれない、多様なジャンルのサービスを知ることができ、聞いているだけでワクワクする発表でした。今回のサービスは、どれもすぐにでも使ってみたいと感じた人が多かったのではないでしょうか。
※本記事で紹介しているWebサービスは、LT登壇者個人の見解です。当社の公式な意見や、特定のサービスを推奨・保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
▼2人目:新田さん (サーバーサイドエンジニア)
「初めてのローコード開発~ローコードがもたらす新しい開発の形~」
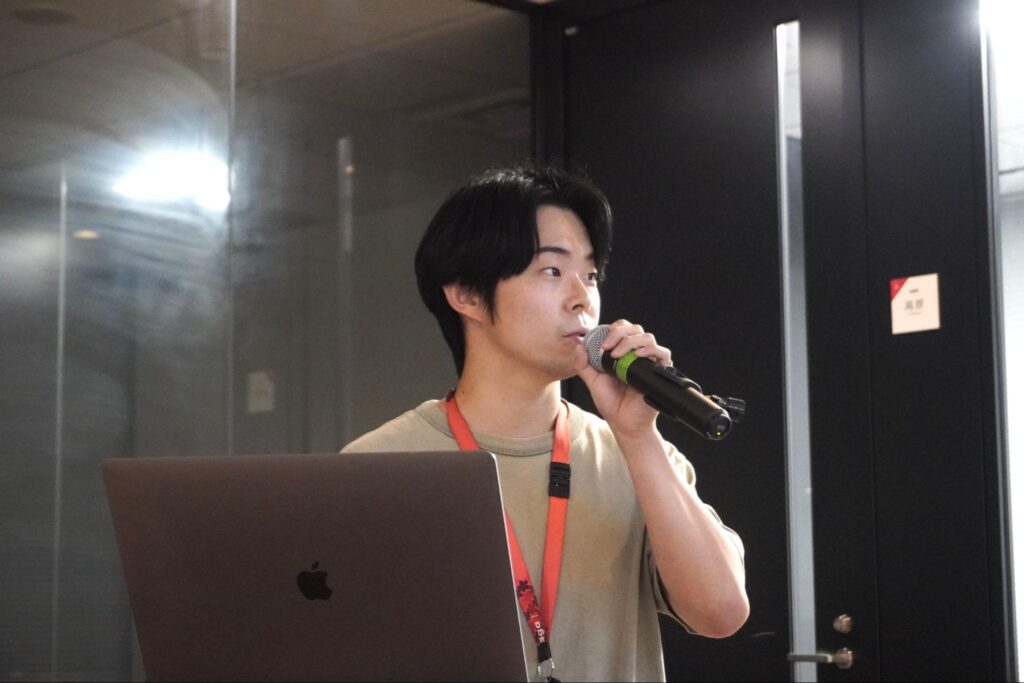
続いて登壇した新田さんは、自身の経験や勉強したことを基に、「ローコード開発」について入門的な内容を発表しました。
ローコード開発とは、GUI(Graphical User Interface)*を用いてプログラミングを最小限に抑え、開発コストを削減できる手法です。基本的な開発の流れは従来のスクラッチ開発と同じですが、設計・開発フェーズは異なります。
新田さんは、ローコード開発において「OOTB(Out Of The Box:標準機能)」をベースにすることの重要性を強調。多くの業界標準フレームワークを採用し、適切な業務プロセスを考慮した製品設計がされているためです。そのため、標準機能から逸脱した過度なカスタマイズは、業務非効率やバグの原因となる可能性があると注意を促しました。
一方で、ローコードには制約やライセンス費用といったデメリットも存在します。そのため、クライアントの要望を標準機能で実現できない場合は、代替案を積極的に提案する姿勢が、今後のエンジニアにとって重要になると締めくくりました。
ローコード開発とスクラッチ開発、それぞれのメリット・デメリットを理解し、顧客に最適な提案をすることの重要性を再認識させられる内容でした。技術力だけでなく、提案力もエンジニアにとって不可欠なスキルなのだと、再認識させられる内容でした。
*GUI(Graphical User Interface):コンピューター画面に表示されるウィンドウやアイコン、ボタンなどをマウスやタッチパネルなどのデバイスで直感的に操作する方式。
▼3人目:戸谷さん(サーバーサイドエンジニア)
「AI駆動開発実践(お試し)中です」

3人目の戸谷さんは、現在進行中の実案件で取り組んでいる「AI駆動開発」について発表しました。特に設計フェーズでのAI活用に焦点を当て、要件定義の成果物をインプットし、AIに設計成果物を作成させるプロンプトの説明をしました。
実際に、Excelで管理されていた100画面もの画面仕様書を、AIにスクリプトを書かせてMarkdown形式に変換したエピソードを紹介。「基本的に何をやるにしても、AIを使って効率化できないか」という考えのもと、まずは試してみることの重要性を語りました。
また、AIを活用する際に、その精度を高めるためには、「コンテキストエンジニアリング」という考え方が重要だと話しました。これは、AIが高い精度の成果物を出すために、必要な背景情報をうまく設計して与えるアプローチです。前工程の成果物を次工程のコンテキストとして連鎖させることで、開発プロセス全体の品質を高められる可能性があります。
AI駆動開発は効率化の可能性がある一方で、現状では成果物の品質チェックは人力に頼っており、レビューがボトルネックになるという課題や、組織全体で取り組むことが重要であるということも語ってくれました。
まさに今、多くのエンジニアが向き合っているAI活用のリアルな話を聞くことができ、非常に参考になりました。「今まで8時間かかっていた仕事が2時間で終わるようになった」という海外事例も紹介され、AI駆動開発の可能性を強く感じさせる発表でした。
▼4人目:藤本さん(コンサルタント・マネージャー)
「なぜ今データなのか」

最後の登壇者は、コンサルティング本部のTech Div.マネージャー藤本さん。今回は、データ活用についての発表でした。アルサーガではデータ活用分野に力を入れており、その一環としてDatabricksのパートナーに選定されています。
関連記事:アルサーガパートナーズ、データブリックスのパートナープログラムにて「Select Tier」に昇格
世界のデータ流通量が爆発的に増加している現状をグラフを用いながら提示し、その中でも動画、音声、文章といった「非構造化データ」が全体の8割を占めているという話からスタートしました。
増え続けていくデータの活用が企業のキャッシュフローに大きな影響を与える一方で、日本企業で全社的にデータ活用に取り組み、十分な成果を上げているのはわずか8%程度という統計もあるとのこと。この現状を裏付けるように、世界の先進国67か国と比較した際、データ活用と分析技術の分野で日本は最低レベルに位置してるとの見方もあるそうです。
藤本さんは、生成AIが普及する現代において、AIをそのまま使うのではなく、自社データとAIを組み合わせることが競争優位性を生む鍵だと強調しました。また、アルサーガパートナーズが提供できるこのデータサービスには、大きな事業ポテンシャルもあるということを改めて共有しました。
さらに、データ基盤の歴史的変遷にも触れ、従来の課題を解決する革新的な技術として「データレイクハウス」を紹介。データとAIの両方を管理できるこの技術が、今後のデータ活用の中心になることを示唆しました。
また、日本企業では、縦割り文化によるシステム統合の困難さと、チャレンジへのためらいが強く、これら2つがデータ活用に躓く理由だと挙げています。「テクノロジーはあくまで手段」であり、ビジネスモデルとデータをどう組み合わせるかが重要だというコメントは、非常に納得できるものでした。
発表内容出典元:
Gartner、日本企業のデータ活用に関する最新の調査結果を発表:全社的に十分な成果を得ている組織の割合は8%
デジタル 経済産業省 大臣官房 若手新政策プロジェクト PIVOT データに飲み込まれる世界、 聖域なきデジタル市場の生存戦略
その他の関連記事:
【Databricks DATA+AI SUMMIT 2025 参加レポート!】イベント概要と現地で感じた熱気をお届け
【Databricks Data + AI Summit 2025 】マーケティングフォーラムレポート
ピザを囲む懇親会

今回も多くのメンバーが参加し、大いに盛り上がりました。 プロジェクトや部署が違う方々とこうした社内イベントを通じて交流の輪が広がるのは、運営として非常にうれしい光景です。
登壇者への質問が飛び交ったり、ピザを頬張りながら発表内容について深く語り合ったりと、今回も有意義な時間となりました!雑談の中から新しいアイデアが生まれることもあるのが、アルサーガの素晴らしい文化です。
おわりに

今回のTOTも、学びと笑いに満ちた素晴らしい会となりました。 TOTは、アルサーガが大切にしている「挑戦を後押しする風土」と「仲間とのつながり」を象徴するイベントの一つです。知の共有の場で誰かが想いを語り、その発表を受け止める仲間と一体となって懇親会の場で新しいアイデアにつながっていくことで、TOTというイベントが成り立っていることがわかります。
このやりとりが新たな気づきを生み、互いの成長につながっていきます。 アルサーガは、これからも挑戦を支え合える文化を育んでいきます。
(文=広報室 白石)
アルサーガに興味を持っていただける方を募集しています!
エントリーしたい方、話を聞きたい方、気軽にお問い合わせください!
ご意見・ご感想募集
この記事へのご意見、ご感想をお待ちしています。
「おもしろかったよ」「もっとこんなことが知りたい」など、どんなご意見でも構いません。あなたのご感想を、ぜひ、こちらのフィードバックフォームからお送りください。




