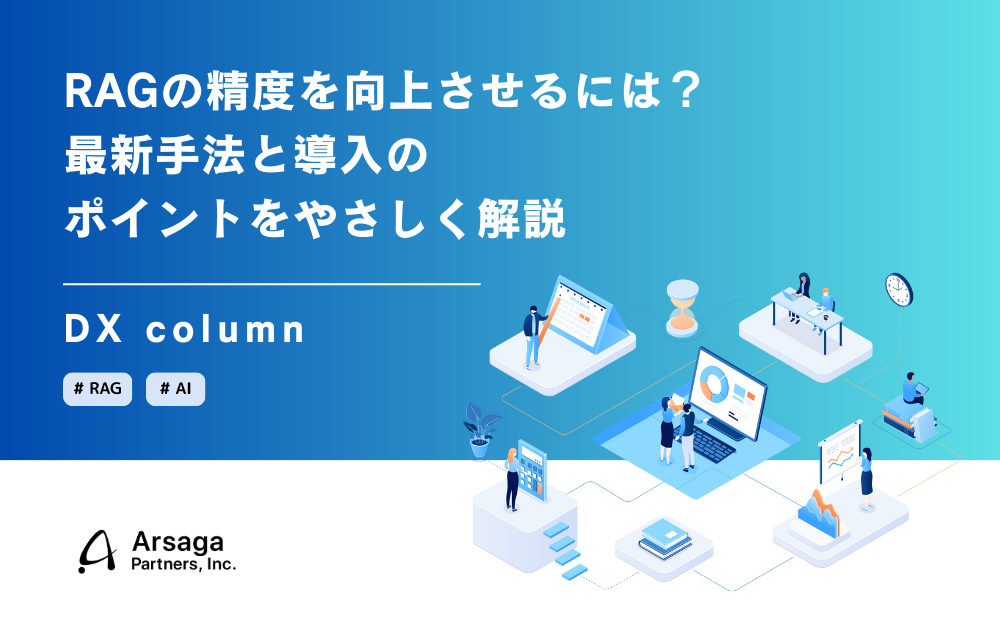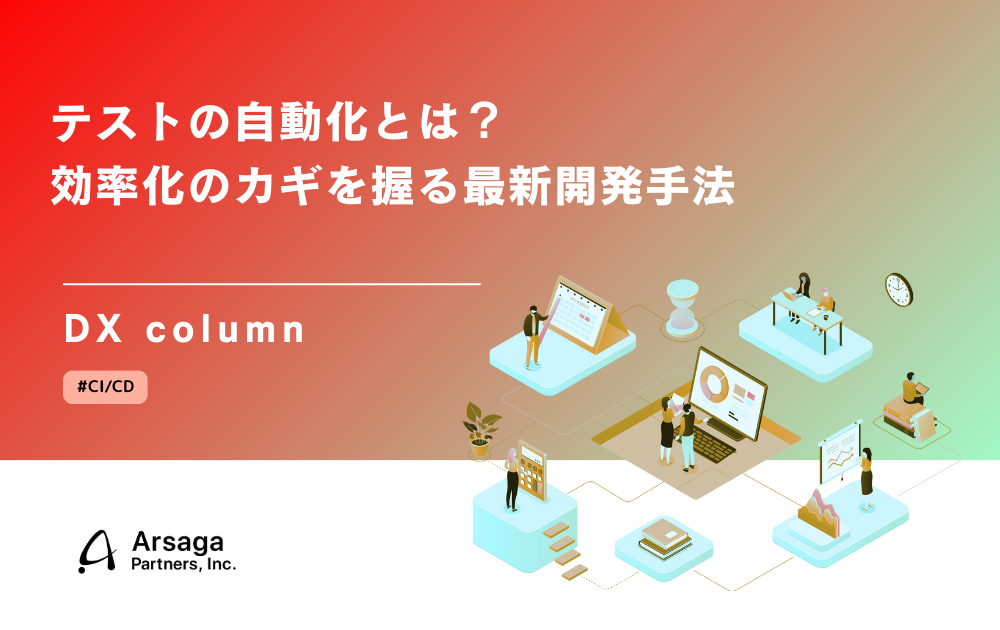動画生成AIが変えるクリエイターの役割変化と活用事例を解説

「動画を作るには時間もお金もかかる。」そんな常識が、今大きく変わろうとしています。近年、生成AIの進化により、テキストや画像から簡単に動画を作成できる技術が登場し、プロのスキルがなくても、アイデアひとつで高品質な動画が生み出せるようになってきました。
この記事では、生成AIが動画制作にもたらす変化や、実際の活用事例、そして今後の可能性について、わかりやすく解説していきます。特に、2024年に発展を遂げ、2025年の現在も進化を続ける技術や、クリエイターの役割の変化に焦点を当てて紹介します。
関連記事:画像生成AIの活用法とは?話題の技術と知っておきたい注意点を解説
生成AIとは?動画との関係を解説

そもそも生成AIとは
生成AIとは、与えられた情報をもとに新しいデータやコンテンツを作り出す人工知能のことです。例えば、ChatGPTのように文章を生成したり、画像を描いたりするAIも、この技術の一つです。人間が一から作るのではなく、AIが補助や代替をすることで、創作や表現の幅を広げてくれます。
もともとは文章や画像の分野で使われることが多かった生成AIですが、今ではその応用範囲が動画にまで広がってきています。
関連記事:ここまで来た!生成AIの最新ビジネス活用事例まとめ
生成AIが動画に応用される背景
動画制作は、一般的に多くの工程を伴います。企画から撮影、編集、ナレーションの録音まで、手間も費用もかかりがちです。特に個人や小規模なチームにとっては、動画制作は高いハードルとなることが少なくありません。この点を生成AIが解決することが強く期待されています。
そこで注目されているのが、生成AIの力を借りた「自動動画生成」。テキストや画像など、比較的簡単に用意できる素材から動画を自動で作成できれば、従来のように人手やコストを大量にかけずとも、質の高い動画を効果的に手軽に生み出すことが可能になります。特にコスト削減においては大きな効果が見込まれます。
こうした背景から、企業や個人を問わず、生成AIを使った動画制作の活用が進んでいるのです。多くのユーザーが、より手軽にクリエイティブな活動をできるようになることが期待されています。
動画生成AIの仕組みと機能
最近では「プロンプト」と呼ばれる短い説明文を入力するだけで、AIが自動的に動画を生成してくれるツールが登場しています。例えば、「走り回る猫」というような簡単な文章を入力するだけで、それに合った風景や動き、構成をAIが判断し、数十秒から数分の映像を作ってくれるのです。
この技術によって、AIが膨大な量の動画データを学習することで、「どんな動きが自然に見えるか」「どの色が適切か」といったことを自分で判断できるようになりました。人間の直感やセンスに頼っていた部分を、AIが補完してくれる、そんなイメージに近いかもしれません。ツールによっては無料で利用できる機能も搭載され始めています。日本語での指示にも対応し、ユーザーにとっての利便性が向上しています。
画像や写真から動画を作る方法
生成AIの技術は、静止画から動画を作る場面でも活用されています。1枚の画像から風が吹いたように髪が揺れる様子や、瞳が動く様子を再現するような技術です。この技術は、人物の表情を豊かに表現する機能としても進化しています。
これは「ディープラーニング」と呼ばれる機械学習の技術を用いて、画像の中の物体を立体的に解析し、「こう動くはずだ」という予測に基づいて動きを加えていく方法です。まるで、写真が命を吹き込まれたかのように動き出すその映像には、思わず目を奪われてしまいます。
音声合成との組み合わせ
さらに進化を見せているのが、音声合成と動画生成の組み合わせです。ナレーションを人の声で録音する代わりに、テキストをAIに読み上げさせることで、映像と音声が一体になった動画を簡単に作成することができます。
最近では、話し方のトーンや感情まで調整可能な合成音声が増えてきており、単なる読み上げではない、自然な会話のような音声が可能になっています。また、オリジナルのキャラクターを設定し、そのキャラクターの声でナレーションを入れる機能も搭載され始めています。
これにより、説明動画や解説コンテンツも、より手軽に、しかも短時間で制作できるようになってきました。
2025年の現在、動画生成AIは特定の機能に特化した種類が発展してきています。例えば、OpenAIのSoraは複雑なシーン構成や物理法則の再現性に優れ、リアルな長尺動画のプロトタイピングに役立ちます。また、RunwayのGen-4やGoogleのVeo 2といった製品は、時間軸の一貫性や人物の表情の自然さを追求しており、商業用途向けのクリエイティブ制作で高い効果を期待できます。これらの具体的な機能を知り、用途に合わせて選ぶことが、顧客の独自性を高める鍵となります。
動画制作のAI活用事例

広告・マーケティング業界
生成AIの導入が最も進んでいる分野のひとつが、広告やマーケティングの世界です。短時間で複数のバリエーションを作れるため、商品やサービスのプロモーションに合わせた動画をすばやく展開できるのが魅力です。
例えば、1本の原稿をもとに、ターゲット層やSNSの特性に応じて異なる種類の動画を自動生成し、A/Bテストを行うという手法が一般化しつつあります。時間や予算の制約が厳しいキャンペーンでも、AIが効率的な動画制作を支えてくれる存在となっています。特に顧客の反応を具体的に検証するためのクリエイティブ制作に効果を期待できます。
具体例として、アルサーガパートナーズが開発支援した、NDPマーケティング提供の「Vista Movie」のようなツールがあります。これは、広告運用者向けの縦型広告動画テンプレート生成AIです。商品情報を入力するだけで、業界に最適化されたテンプレートに基づき、最短3分で5パターンの動画を自動生成します。これにより、1本あたりの制作コストを従来の数万円から数百円レベルにまで大幅に削減し、A/Bテストを迅速かつ大規模に行うことを可能にしました。
関連プレスリリース:https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-vistamovie-20250217/
教育・研修動画への応用
教育分野でも、生成AIは着実にその存在感を増しています。授業動画や研修コンテンツの作成には、説明資料・ナレーション・編集作業など、多くのステップが必要とされてきました。
しかし、生成AIを用いれば、スライド資料を読み込ませるだけで解説付きの動画が完成するというケースもあります。講師の声をAI音声で再現することもできるため、個別の対応や多様な言語への展開も比較的スムーズに行えるのが特徴です。
特にeラーニングや社内研修のように「内容は同じだけど対象が変わる」場面では、大幅な効率化が可能となります。これは、教育向けの製品として広く紹介されており、学習効率の向上に役立ちます。
SNSやYouTubeコンテンツの自動生成
日々新しいコンテンツが求められるSNSやYouTubeの世界でも、生成AIの力が注目されています。定期的な投稿が求められる中で、話題性のあるテーマに合わせてAIが即座に動画を構成・編集してくれるため、コンテンツの量産が可能になります。
例えば、AIがニュース記事を要約し、それをもとにナレーションと画像を組み合わせて動画に仕立てるといった使い方が増えてきています。こうした自動化によって、少人数でもチャンネルの運営を継続できる環境が整いつつあるのです。この用途に合わせた種類の製品を選ぶことが重要です。
動画生成AIのメリットと注意点
◎コスト削減とスピードアップ
生成AIを使った動画制作の最大の利点は、やはり「手間が大幅に省けること」にあります。従来、動画を作るには撮影機材や編集ソフト、人手が不可欠でした。ナレーションを入れるだけでも、声優や録音スタジオの手配が必要になることもありました。
しかし、生成AIを使えば、企画から完成までの時間が圧倒的に短縮されます。素材を入力すれば自動でナレーション付きの動画が完成する、そんな便利な時代がすでに始まっているのです。これにより、トータルのコスト削減が期待できます。
また、繰り返し使えるテンプレートやAIモデルを利用することで、制作コストも最小限に抑えられるようになります。これは特に中小企業や個人クリエイターにとって大きなメリットです。一部の製品は無料のプランも提供しています。
△著作権・倫理的な課題
一方で、便利さの裏には注意すべきポイントもあります。特に近年問題視されているのが「著作権」と「倫理性」です。これが動画生成AIの大きなリスクとなっています。
AIが学習に用いたデータの情報源が不透明である場合、その生成物にも著作権上の問題が発生する可能性があります。例えば、既存の映画やアニメの映像に酷似した表現が偶然出力された場合、権利侵害とみなされることもあります。また、商用利用の可否は製品ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
また、人の顔や声を模倣して動画を生成する「ディープフェイク」技術も含まれるため、意図しない誤解や悪用を防ぐための配慮が求められます。生成した動画の利用にあたっては、出典の明記や説明責任を果たす姿勢が必要です。複雑化するリスクへの対策として、提供元によるサポート体制の強化も求められています。
つまり、生成AIを使う際には「何ができるか」だけでなく「どう使うか」にもしっかりと目を向ける必要がある、ということですね。
生成AIと動画制作の未来

プロとAIの共創が主流になる?
生成AIの進化によって、「動画を作る人」の役割そのものも少しずつ変わってきています。かつては、撮影・編集・ナレーションなど一人では完結できなかった工程が、今ではAIとの連携によって一人でもこなせるようになりました。
しかし、これは「人間の仕事がAIに取って代わられる」という話ではありません。むしろ、AIは道具として、制作者のアイデアや表現力を広げる存在になってきているのです。いわば、人間とAIの“共創”というスタイルが、これからの動画制作の主流になっていくのかもしれません。
例えば、AIが生成したラフ動画をもとに、プロのクリエイターがディテールを整え、最終仕上げを行うといった形。時短をしつつも、クオリティには妥協しないという新たな制作の形が生まれつつあります。2025年現在、よりリアルな映像生成を可能にする機能の搭載が進んでおり、さらなる進化が期待されています。
クリエイターの役割はどう変わるか
生成AIの普及によって、動画クリエイターには新たな視点やスキルが求められるようになっています。従来の「技術力」だけでなく、「AIをどう活かすか」という戦略的な視点が重要になってきているのです。AIを使いこなすための知識も必要とされます。
また、企画や構成といった“考える力”や、視聴者の心をつかむ“ストーリーテリング”の力もより重視されるようになりました。ツールとしてのAIは、これらのクリエイティブな作業に集中できるように役立ちます。
2025年の現在、知識と設定がクリエイティブの成否を分けます。AIがどれほどリアルで美しい映像を生成しても、その映像に人間的な感情の機微や共感を呼ぶ物語を吹き込むのは、依然としてクリエイターの役割です。
従来の「撮影・編集技術」に加え、今後は「AIの限界を見極める知識」と「プロンプトという新しい言語でアイデアを具現化するスキル」、そして「生成された多様な映像ピースを複雑な感情線に沿って再構成する選択力」が不可欠となります。これこそが、AI時代における独自性の源泉であり、クリエイターの価値をさらに高める点となります。
AI時代に求められるクリエイターの視点
生成AIの進化によって、動画制作はこれまでにないスピードと柔軟性を手に入れました。個人も企業も、より自由に、より効率的に動画を生み出せる時代が始まっています。
とはいえ、その便利さの裏には著作権や倫理の問題といったリスクも潜んでいます。AIを道具としてうまく使いこなすためには、技術だけでなく視点と判断力も欠かせません。
これからの動画制作においては、「AIに任せる部分」と「人間だからこそできること」のバランスを見極める力が、ますます重要になっていくでしょう。
関連記事:
画像生成AIの活用法とは?話題の技術と知っておきたい注意点を解説
ここまで来た!生成AIの最新ビジネス活用事例まとめ
(文=広報室 白石、編集=広報室 宮崎)