
DXコラム
DXコラム
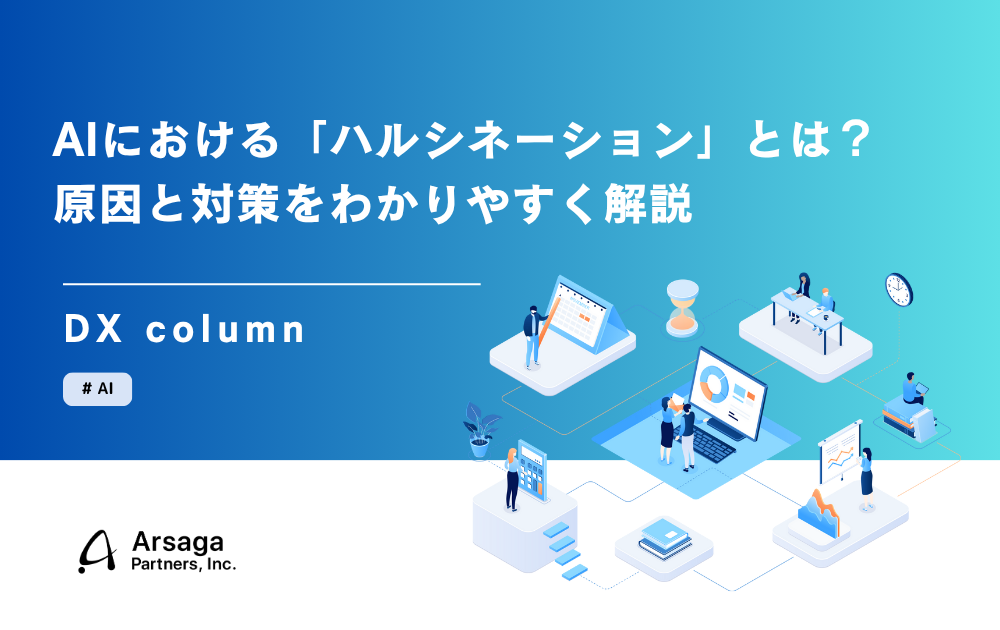
AIと聞くと、正確な情報を瞬時に提示してくれる便利なツールという印象を持つ方が多いでしょう。質問をすればすぐに答えを返し、要約や提案もこなすその姿は、まるで頼れるアシスタントのようです。
しかし、その便利さの裏側には見過ごせない課題があります。AIはときに、事実とは異なる内容を、あたかも本当のように生成してしまうという側面があります。
この現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、人間が幻覚を見るように、AIが根拠のない情報をもっともらしく作り出す状態を指します。文章が自然で説得力を持つほど、誤情報を信じてしまう危険性は高まります。
AIは社会の効率化や創造性を支える存在である一方、ハルシネーションのような課題とどう向き合うかが、今後のDX推進における重要なテーマです。
本記事では、この現象の仕組みと原因、そして信頼できるAI活用に向けた考え方を整理していきます。
目次
ハルシネーションとは、AIが事実とは異なる情報や根拠のない内容を、あたかも正確であるかのように生成してしまう現象を指します。もともとは「幻覚」を意味する英語「hallucination」に由来し、人が見えないものを見てしまう状態になぞらえた言葉です。
AIが作り出す文章は自然で説得力があるため、誤った情報であっても真実のように感じられてしまうことがあります。特に構成や語り口が整っている場合、読む側が無意識のうちに「正しい」と受け取ってしまうこともあります。
ただし、AIが提示する内容のすべてに事実や根拠があるわけではありません。出典が示されないまま存在しない研究や論文、架空の事例が提示されることもあります。こうした誤情報が拡散すれば、利用者の判断を誤らせたり、社会的な信頼を損なう危険もあります。
AIが生み出す情報の正確さを前提にするのではなく、それがどのような背景や仕組みのもとで生成されたのかを見極める視点が求められます。
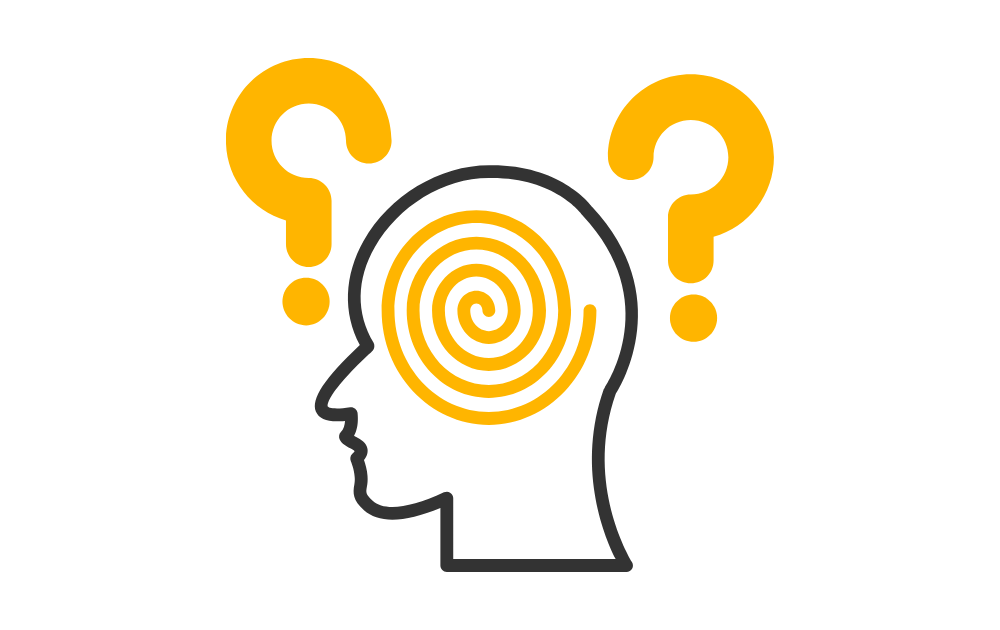
AIがハルシネーションを起こす理由には、いくつかの要因が絡み合っています。いずれもAIの仕組みに根ざしたものであり、現時点では完全に防ぐことが難しい問題でもあります。ここでは、主な3つの原因について見ていきましょう。
AIは大量の文書データを基に言語の傾向を学習しています。そのため、学習に用いられたデータに誤りや偏りが含まれていると、その影響を受けやすくなります。特にインターネット上の情報は信頼性が一定ではなく、不正確な内容をそのまま取り込んでしまうこともあります。
また、AIは学習時に得た知識を基に出力を行うため、学習データに含まれていない情報には対応できません。新しい出来事や最新の研究成果に関する質問を受けた際、AIは「それらしく見える」答えを補おうとします。このとき、実際には存在しない情報を、自然な文章として生成してしまうことがあります。
このように、AIの知識はあくまで過去のデータに依存しており、更新されない限り、新しい情報を正確に反映することはできません。学習データの限界は、AIの正確性を左右する根本的な要素の一つと言えます。
AIは、次に続く言葉を確率的に予測しながら文章を組み立てています。この仕組みは高性能ですが、意味の正確さよりも文脈上自然に見える表現を優先する傾向があります。そのため、もっともらしい文章を作ることは得意でも、その内容の真偽を判断しているわけではありません。
その結果、AIは整った文章を生成しながらも、根拠のない情報を含んでしまうことがあります。特に、質問に明確な答えが存在しない場合、AIは「それらしく見える」形を補おうとし、誤った結論を導いてしまうことがあります。
AIの出力は統計的な予測に基づいており、論理的な検証や事実確認を経て導かれたものではありません。表現の自然さと情報の正確さが必ずしも一致しない点が、ハルシネーションを生じさせる大きな要因となっています。
AIは、自分が生成した情報の正しさを確かめることができません。与えられたデータをもとに自然な文章を作ることは得意ですが、その内容が事実に基づいているかどうかを判断する力は持っていません。
そのため、AIの文章は一見滑らかで説得力があっても、根拠のない内容を含んでいる場合があります。特に、専門的な分野では、正確さよりも言葉の整合性が優先され、誤情報を自信を持って提示してしまうことがあります。
AIの出力を信頼するためには、内容をそのまま受け入れず、根拠や出典を確かめる姿勢が欠かせません。「最終的な判断を担うのは、常に人間である」という意識が求められます。

AI社会におけるハルシネーションは、理論上の話ではなく、既に現実の問題として多くの場面で確認されています。ここでは、AIが事実ではない情報を自然な形で提示してしまった代表的な事例を3点取り上げます。
AIに参考文献を尋ねると、もっともらしい書籍名や論文タイトルを提示することがあります。しかし、その中には実際には存在しないものも含まれています。タイトルや著者名は本物のように見えても、検索しても見つからないという状況が起きています。
これは、AIが質問内容に合いそうな文献情報を組み合わせ、整った形式に仕上げてしまうことが原因です。構文のパターンをもとに「それらしく見える」出典を作り出してしまうため、実在しない情報が自然な形で生成されてしまいます。
このような事例は、AIの出力をそのまま引用したり、内容を確認せずに利用したりすることのリスクを示しています。情報の出典を検証する習慣を持つことが、AIを適切に活用するための第一歩と言えます。
医療や法律のように、情報の正確さが特に重要な分野でも、ハルシネーションは問題となっています。あるユーザーが特定の病気の治療法を尋ねたところ、実際には存在しない薬や手順が示されたという報告があります。もし、それを信じて行動すれば健康被害や誤った判断を招くおそれがあります。
法律の領域でも同様の例が見られます。アメリカでは、弁護士がAIに裁判資料の作成を依頼した際、提示された判例の中に架空のものが含まれていたことが判明しました。この出来事を受けて、裁判所はAIの利用に関して慎重な対応を求めています。
これらの事例は、AIがどれほど自然で説得力のある文章を作成しても、内容が事実に基づいているとは限らないことを示しています。正確さが問われる分野では、AIの出力をそのまま使わず、人間が最終的に確認する姿勢が欠かせません。
AIは特定の人物や企業に関する質問に対しても、事実と異なる情報を生成してしまうことがあります。たとえば、実際には発言していない内容を本人の言葉として示したり、誤った経歴を提示したりするケースです。
こうした誤情報がSNSやブログを通じて拡散すると、名誉の損失や風評被害につながるおそれがあります。特に企業や著名人に関する内容では、一度広まった情報を修正することが難しく、影響が長期に及ぶ場合もあります。
AIの出力を信頼する際は、文章の自然さにとらわれず、出典や根拠を確かめる姿勢が欠かせません。複数の情報源を確認することが、誤情報の拡散を防ぐための基本になります。

ハルシネーションは、現時点では完全に防ぐことが難しい課題ですが、使い方を工夫することでリスクを抑えることは可能です。ここでは、ユーザーと開発者のそれぞれの立場から、どのように向き合うべきかを整理します。
AI開発の現場でも、ハルシネーションを抑えるための多角的な試みが続けられています。代表的なものとして、出力内容の信頼度を数値化して示す仕組みや、参照元を自動的に表示する機能の導入が挙げられます。これにより、ユーザーが情報の出どころを確認しやすくし、誤情報を見抜く手がかりを提供することを目指しています。
さらに、AIが学習に用いるデータの質を高める取り組みも進行しています。偏りや誤りを含むデータを除外し、より厳密に精査された情報をもとに学習させることで、出力の正確性を高めようとする動きです。加えて、生成過程の中で矛盾を検出し、内部で自己修正を行う仕組みの研究も進められています。
しかし、AIは統計的な予測に基づいて文章を構築する仕組みであるため、事実確認を完全に自動化することは容易ではありません。現段階では、最終的な判断を人間が担い、出力内容の妥当性を見極める責任を持つことが求められます。技術の進歩とともに精度は向上していますが、人間の関与を前提とした開発姿勢は今後も欠かせません。
AIの活用目的によって、ハルシネーションの影響度は大きく異なります。企画の構想づくりや文章の下書きなど、内容を人間が後から修正する前提の用途では、多少の誤りがあっても問題になることは少ないでしょう。AIの発想力や表現の幅を生かしながら、人間が方向性を整えるような使い方が適しています。
一方で、医療や法律、報道といった分野では、情報の正確性が社会的な信頼と直結します。こうした領域では、AIをあくまで参考情報として位置づけ、最終的な判断を人間が行う体制を維持することが欠かせません。
重要なのは、AIをどのような目的で使うかによって、求められる検証の深さや確認の工程が変わるという点です。利用の意図とリスクの関係を理解し、適切な範囲で活用することが、安全で効果的なAIの運用につながります。
ハルシネーションは、事実とは異なる情報をあたかも正確であるかのように生成してしまう現象です。技術が進化するほど文章の精度や説得力が高まり、誤りを見抜くことが難しくなっています。AIの出力は常に「正しい」とは限らないという前提を持ち、情報を受け取る側が主体的に確認する姿勢が欠かせません。
AIを活用するうえで重要なのは、結果を鵜呑みにするのではなく、内容の根拠や出典を確かめる意識を持つことです。便利な道具としての力を最大限に発揮させるためには、使う人間が情報の扱い方を理解し、適切に判断する力を備えている必要があります。
AIを使いこなすというのは、単に効率を高めることではなく、技術と人の知恵を組み合わせて新たな価値を生み出すことです。そのために求められるのは、仕組みへの理解と慎重な検証、そして柔軟な発想です。AIと人がそれぞれの強みを生かし、補い合う関係を築いていくことが、今後の社会における持続的な成長につながっていくでしょう。
関連記事:
AIの進化に法律はどこまで追いつける?AIと私たちの未来
ここまで来た!生成AIの最新ビジネス活用事例まとめ
(文=広報室 佐々木)