
DXコラム
DXコラム
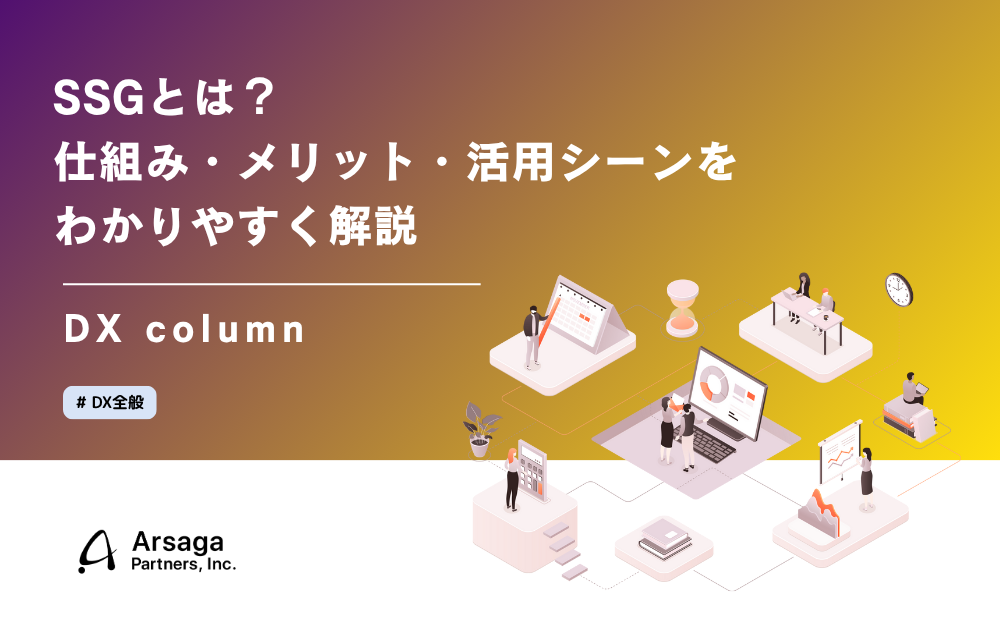
「ページの表示が速くなる」「SEOに強い」「運用コストを抑えられる」そんな理由から、近年「SSG」という技術が注目を集めています。Web制作やフロントエンドの現場では、すでに多くのプロジェクトで活用されており、静的サイトの新しい形として定着しつつある印象です。
とはいえ、「そもそもSSGって何?」「他の方法と何が違うの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「SSG」の仕組みやメリット、向いているサイトの種類などを初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。もしあなたが、表示速度やSEOに悩んでいるなら、SSGがそのヒントになるかもしれません。
目次

SSGは「Static Site Generation(静的サイト生成)」という技術の名前です。WebサイトのHTMLファイルをあらかじめ生成しておき、それをそのままユーザーに配信する手法を指します。
これまでのWeb開発では、サイトを見たいという要求が来てからサーバーがHTMLをその場で作るという「動的生成」が一般的でした。しかしSSGでは、事前にHTMLを完成させておくため、表示が非常に速く、サーバーへの負担も軽く済むという大きな利点があります。
SSGでは、コンテンツを公開する前の「ビルド(構築)」の際に、すべてのページをHTMLとして生成します。
ユーザーがページにアクセスするときには、すでに完成されたHTMLファイルがサーバーやCDN(コンテンツ配信ネットワーク)から即座に提供されるため、処理の遅延がほとんどありません。
たとえば、ブログ記事や商品一覧ページなど、内容が頻繁に変わらないものはこの方式に非常に適しています。生成されたファイルは単なるHTMLなので、どんなデバイスからでも軽快に表示されるのが特徴です。
SSGという言葉が本格的に広まった背景には、「JAMstack(ジャムスタック)」という設計思想(考え方)の登場が大きく影響しています。JAMstackでは、JavaScript・API・Markupの3つを組み合わせてWebアプリケーションを構築しますが、この「Markup」の部分がまさにSSGによって支えられています。
また、Next.jsやNuxt.jsといったモダンなフレームワークでは、SSGの仕組みが標準機能として用意されており、開発者が簡単に導入できるようになっています。静的なコンテンツであっても、技術的にはとても柔軟で拡張性のある環境が整ってきているのです。
SSGでは、Webサイトの各ページを「ビルド(構築)」という工程であらかじめ生成しておきます。このとき、ページの元となるデータはCMSやMarkdownファイル、外部APIなどから取得され、それらの情報を元にHTMLファイルが静的に作られます。
SSGは、Webサイトのコンテンツを「作り置き」するようなものです。
【わかりやすくお弁当に例えたイメージ】
記事データ(材料)を集めて、ビルド時(調理時間)に完成されたHTML(お弁当)を作っておきます。ユーザーがアクセスする(注文が入る)と、すぐに完成品(お弁当)を渡すだけなので、待ち時間がほとんどありません。
開発者の立場からすると、「Webアプリケーションを動的に動かす」のではなく、「Webページそのものを公開前に作っておく」というイメージです。
ビルド後のファイルは、基本的にサーバーやCDNに配置されます。ユーザーがWebサイトを閲覧すると、その要求に対してサーバーはHTMLファイルを即座に返すだけで済みます。
その結果、リクエストごとに計算処理を挟む必要がなく、応答速度が非常に速くなるのがSSGの特長です。また、CDNを活用すれば、世界中どこからアクセスしても近くのサーバーからファイルが配信されるため、グローバルなユーザー体験の向上にもつながります。
SSGは、他の代表的なレンダリング方式である「SSR(Server Side Rendering)」や「CSR(Client Side Rendering)」とよく比較されます。
| 項目 | SSG (静的サイト生成) | SSR (サーバーサイドレンダリング) | CSR (クライアントサイドレンダリング) |
| HTMLを作るタイミング | アクセスが来る前 (ビルド時) | アクセスが来るたび | アクセスが来た後 (ブラウザ内) |
| 表示速度 | 最速 | やや遅い | 初回表示が遅くなりがち |
| サーバーの負荷 | 極めて低い | 高い | 低い |
| SEOの強さ | 非常に強い | 強い | やや弱い |
| リアルタイム性 | リアルタイム更新は苦手 | 常に最新の情報を表示 | リアルタイム更新が得意 |
| 向いてるサイト | ブログ、企業サイト、LPなど | ECサイト、会員向けサイトなど | ユーザー操作が多いアプリ |

SSGの最大の魅力は、ページの表示が非常に速いという点です。あらかじめ生成されたHTMLファイルをそのまま配信するため、ユーザーの要求に対して即座に応答できます。特にスマートフォンなど通信環境が不安定な場面でも、軽量なHTMLが高速で読み込まれるので、ストレスなく閲覧できるというメリットがあります。
これは、訪問者の離脱率の低下や、コンバージョン率の向上にも直結します。つまり、ビジネスにおいても「表示の速さ」は無視できないポイントなのです。
SSGはSEOにも効果的です。なぜなら、最初からHTMLが完成された状態で配信されるため、Googleなどの検索エンジンがコンテンツを正確に認識しやすいからです。
一方で、JavaScript主体で後から内容を読み込むようなCSR方式では、検索エンジンがコンテンツをうまく取得できず、インデックスされにくいことがあります。SSGであれば、タイトルやメタデータなどを確実に反映させられるため、安定したSEO効果を得やすい傾向にあります。
SSGでは、ユーザーごとにHTMLを生成する必要がないため、サーバー側の処理が極端に少なくなります。その結果、トラフィックが急増した場合でも安定したパフォーマンスを維持しやすく、サーバーがダウンするリスクも低く抑えられます。
さらに、データベースへの接続や複雑なログイン処理などを介さないため、セキュリティリスクも軽減されるのが特長です。CMSの脆弱性による攻撃を防ぎたいという理由で、SSGに移行する企業も増えています。また、ホスティングも軽量で済むため、運用コストを削減できるのも大きな利点です。
SSGは開発者にとっても扱いやすい構成です。CMS(Contents Management System)などの管理画面と表示側を切り離して構築できるため、開発と運用の役割を明確に分けやすくなります。
たとえば、記事や製品情報はヘッドレスCMSで管理し、ビルド時にその内容を取り込んで静的なページを生成するという方法が一般的です。これにより、エンジニアではない担当者が更新作業を行いつつ、表示側は高速で安定したサイトを維持できるという体制を整えることが可能です。

SSGは「事前にすべてのページを生成しておく」方式であるため、リアルタイムに変化するコンテンツとは相性がよくありません。
たとえば、リアルタイム株価、ニュース速報、ログイン後のダッシュボードなど、「人によって表示が変わる」情報や「頻繁に更新される」情報とは相性がよくありません。その都度ビルドをやり直す必要があるため、頻繁な更新が求められる場合は別の手法(例:ISRやSSRなど)と組み合わせることが必要になります。
ページ数が少ないうちは快適ですが、数百・数千ページに及ぶ大規模サイトになると話は別です。生成すべきページが多いほど、ビルド時間が長くなり、更新のたびに待ち時間が発生してしまいます。
特にECサイトや多言語サイトなどでは、このビルド工程がボトルネックになることも。そのため、ビルド時間を短縮する工夫(差分ビルドやキャッシュの活用)や、動的レンダリングとの併用が必要になる場合があります。
SSGでは、すべてのユーザーに対して同じ内容のHTMLを提供することを前提としています。そのため、ログインユーザー専用の情報や、閲覧履歴に応じたおすすめ表示など、「ユーザーごとに異なる情報を表示する」といった要件には適していません。
こうした個別性の高いページは、クライアントサイドでの処理やサーバーサイドとの連携が必要になります。つまり、SSG単体では対応が難しい場面もある、ということです。

SSGの特性を最も活かせるのは、「コンテンツの更新頻度がそれほど高くなく、構造が決まっている」タイプのサイトです。
たとえば、技術ブログや製品ドキュメント、企業のコーポレートサイト、キャンペーンのLP(ランディングページ)などはその代表例。あらかじめ決まったレイアウトで情報を表示でき、アクセスが集中したときにも安定して高速な表示が可能です。
SSGは、CDNとの相性がとても良い構成です。生成された静的なファイルを世界中のエッジサーバーにキャッシュさせることで、どこからアクセスしても安定した表示スピードを実現できます。
特に、海外市場向けに複数言語でサイトを展開しているようなケースでは、その恩恵が大きくなります。各地のCDNノードで配信することで、世界中のユーザーに快適な閲覧体験を届けられます。
SSGを実現するためのフレームワークは年々進化しており、いまでは選択肢も豊富です。
・Next.js:Reactベースで、SSGとSSRを柔軟に切り替えられます。更新の効率を高めるISR(Incremental Static Regeneration)もサポート。
・Nuxt.js:Vueベースのフレームワークで、静的サイトとしてのビルドも容易に行えます。
・Astro:非常に軽量で、複数のフレームワークを混在させられる次世代のSSGツール。
・Gatsby:Reactベースで、GraphQLと連携した静的生成が得意。CMSとの統合も簡単です。
SSGが最適な選択かどうかを判断するには、まずサイトの特性を見極めることが重要です。
| 質問 | SSGに向いている場合の答え |
| サイトの更新頻度は高いですか? | いいえ(週に数回や月に数回程度) |
| ユーザーごとに表示内容を変える必要がありますか? | いいえ(全員に同じ内容を見せる) |
| SEOを重視したいページですか? | はい |
| ページ数は非常に多いですか? | いいえ(数百〜数千程度) |
このように、用途に応じて「SSGのみで対応できる範囲」と「別の方式を組み合わせた方がよい範囲」を整理することが、導入成功への第一歩です。
規模の大きなサイトでは、ビルドにかかる時間が課題になることがあります。そんなときは、以下の工夫が役立ちます。
・差分ビルド:更新があったページだけを再生成する仕組みを取り入れる(Next.jsのISRなど)
・キャッシュ戦略:CDNを活用し、できる限りエッジ側で応答させることで、再ビルドの頻度を抑える
・デプロイパイプラインの最適化:CI/CDと連携し、スムーズにビルド~公開までを自動化する
SSGはすべてを静的にまかなう構成ではありません。動的な部分は、以下のような方法で補完できます。
・JavaScriptでのクライアントサイド描画:天気情報や最新コメントなどは、クライアント側で取得して表示
・フォーム送信やログイン処理:Jamstack向けのフォームサービスや、Auth0のような外部認証ツールを活用
・部分的にSSRを併用する構成:Next.jsなどを使えば、一部のページだけをSSRにすることも可能
静的サイトだからこそ、検索エンジン対策や高速配信の設計はしっかり行いたいところです。
・メタデータや構造化データの明示的な設定:HTMLを生成する段階で、適切にSEO要素を埋め込む
・CDNとの統合:NetlifyやVercelなど、SSG向けのCDN付きホスティングサービスを選ぶ
・Git連携による自動デプロイ:変更をコミットすれば即ビルド&反映されるようにしておくと、運用効率が飛躍的に高まる
SSGは、あらかじめHTMLを生成しておくことで、表示速度の向上やサーバー負荷の軽減、SEO対策の強化といった多くのメリットをもたらす技術です。特に、更新頻度の低いWebサイトや、ブログ・ドキュメント・企業サイトなど、静的コンテンツが中心のプロジェクトには非常に適しています。
一方で、リアルタイム性が求められる機能や、大量のページを持つサイトでは、ビルド時間や柔軟性の面で制約も出てきます。そういった場合には、動的レンダリングやクライアントサイド処理と組み合わせることで、SSGの弱点を補うことが可能です。
導入にあたっては、サイトの目的や運用体制を見直しながら、SSGが本当にフィットするかを慎重に見極めることが大切です。そして、Next.jsやNuxt.js、Astroなどの優れたフレームワークを活用すれば、より実用的かつ効率的なWebサイト構築が実現できます。
もし、あなたが「ページを速くしたい」「SEOを強化したい」「運用コストを抑えたい」と考えているのであれば、SSGは検討する価値のある選択肢です。まずは小さなサイトや一部のページから導入してみて、SSGのメリットを実感してみるのも良いかもしれません。
(文=広報室 宮崎)
あわせて読みたい記事:
・ウェブアクセシビリティを分かりやすく解説!
・DevOpsとCI/CDの違いとは?初心者でもわかる開発プロセスの基本