
Techブログ
Techブログ
〜現場起点でつくる、自走するデータ人材の育て方〜
今回は、筆者が以前在籍した外資系コンサルティングファームで、データサイエンティストとして担当した『データサイエンス教育プロジェクト』の経験をご紹介します。
実際に現場で起きた課題や取り組みの中から、データ人材育成のリアルをお伝えできればと思います。

「データ活用」が企業経営の要とされる今、多くの企業がその波に乗ろうとしています。しかしながら、現場の実情を見ると、「期待したほど成果が出ない」という悩みが数多く聞こえてきます。特に、現場の担当者が本当に必要としている分析結果と、データ分析者が提供するアウトプットの間にズレが生じることがよくあります。
本記事では、実際のプロジェクトにおいて筆者が直面した課題と、それに対してどのような対応を行ったのか、、具体的な事例を交えながら紹介していきます。
目次
この企業では、社内のデータ活用を本格化させるために、段階的にデータ人材を育てていく仕組み(Wave制)を採用していました。
・Wave1:データにある程度慣れている社員約50名を選抜し、データサイエンス教育を実施
・Wave2:Wave1の中から指導者を育成し、その指導のもと、約200名に教育を展開(指導者1人あたり5~10人程度担当)
・Wave3以降:さらにその200名の中から選抜して別の200名に教育してく
データサイエンス教育は事前に基礎知識をWeb研修で身につけてもらい、実務教育を指導者が伴走しながら実施していくものでした。実務教育の題材はその企業の困りごとを用いることでデータサイエンス教育の実施と困りごと解消を狙えるものでした。
筆者はこの中で、現場課題のヒアリング、実務教育向けの案件設計、教育ロードマップの策定、Wave1の伴走支援、およびWave2以降の指導者支援を担当しました。

まず筆者は、現場の困りごとをヒアリングし、この企業所属のデータサイエンティストと実務教育の題材を決定しようとしました。
現場の切実な課題を分析テーマとして提示したところ、「その問題は既に現場から受けており、自分たちデータサイエンティストが対応済みである。新たに分析案件化することは不要」といった回答が続発しました。一方で、現場からは「社内の分析では本質的なニーズが汲み取られていない」と、再分析を求める声が上がっていました。
これは、データサイエンティストの現場理解が不十分なまま進行したことで、認識にズレが生じてしまった例です。こうしたギャップこそが、データ利活用が成果に結びつかない大きな要因の一つと言えます。
特に、関係者と綿密なコミュニケーションをしないデータサイエンス案件では、現場の細かなニーズを把握するのが難しいこともあります。そのため、丁寧なヒアリングを重ね、時には現場の作業を実際に見に行くことで、「現場の課題」と「データサイエンティストの視点」をすり合わせることが欠かせません。意識のズレを少しずつ埋めていくことが重要です。
そうした点において、この企業が推進していた「現場をよく知る人材をデータ人材として育成する」という方針は非常に有効でした。
現場に精通した人がデータサイエンスを学ぶことで、データサイエンスで「できること/できないこと」の見極めができるようになります。その結果、必ずしもデータサイエンスだけに頼らない、より実践的な解決方法にたどり着ける可能性も大いにあります。

次に行ったことは、実務教育の題材となる「分析案件」の整理とその具体化、そしてプロジェクトのスケジュール作成です。
「どのように分析を設計すれば現場の困りごとを解決できるか?」をプログラム受講者と一緒に考えるプロセス自体が、現場の思考をデータドリブン化することに一役買います。そのため、ここでは大まかな方針 (どのようなモデルを使うかの参考、一般的な進め方・スケジュール) を作成し、現場と対話しながら調整を行いました。
Wave1では、数多くの課題が浮き彫りになりましたが、特にスケジュール管理の甘さは痛恨でした。最終的に、当初設定した分析アウトプットの半分程度しか到達しませんでした。
この問題に対処するために、Wave2以降では企業と議論し、アジャイル開発手法を取り入れることにしました。小さなスプリントを設定し、各スプリントで進捗を確認し、成果物を評価します。これにより、問題を早期に発見でき、進捗が遅れている場合でも柔軟に調整を加える体制を整えました。また、スプリント終了後には、現場担当者からのフィードバックを反映させることで、必要な修正が迅速に行えるようになりました。

Wave1では、データの所在がわからず、時間を無駄に消費してしまうことがありました。この経験から、改めて「整備されたデータ基盤の重要性」を痛感しました。
Wave2が始まる前に、企業の担当者の迅速な対応により、データ置き場が整理され、この問題は無事に解消。以降はスムーズな教育実施が可能となりました。迅速に対応いただいた担当者の方々には感謝しています。
また、この企業では「現場に詳しい人材をデータ人材として育成する」方針を全社的に掲げているため、データサイエンス教育プロジェクトの受講は優先度の高いものとして認識していました。しかし、実際に参加するメンバーは現場でも重要な立場の方が多く、Wave1でのプロジェクトの参加率が低いことが判明しました。
この状況を受け、プロジェクトの意義や目的を改めて企業の担当者から参加者の上長に説明していただき、参加の優先度を上げていただくことで、より多くの方の積極的な参加につなげることができました。
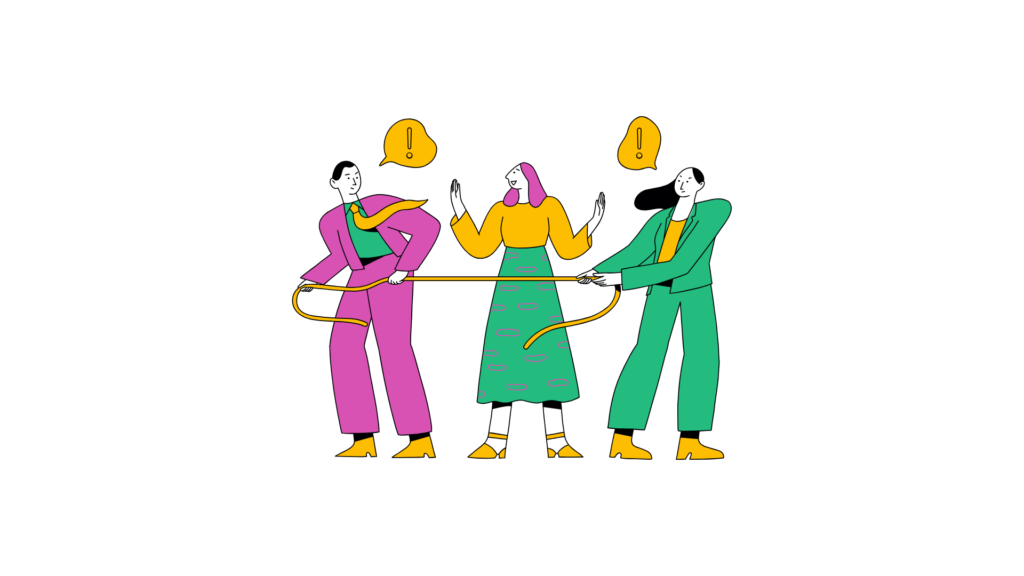
実務教育を終えたら、今度は受講生が現場で活躍する場です。とはいえデータサイエンスの分析案件を1回経験した程度では自走することは難しいのが現実です。しかしながら一度でも分析を経験した仲間が社内にいることで、「分析できる人が誰か分かる」「相談できる相手がいる」状態が生まれ、データ活用の文化が社内に根付き始めました。これは、単発の教育では得られない、実務教育が現場にもたらす最も大きな価値の一つです。
データサイエンティストの育成は、スキルの向上だけでなく、現場に即した知識をどのように活かすかが重要です。現場のニーズを正確に捉え、データサイエンティストと現場担当者の意見を調整し、スケジュール管理や進捗管理をしっかり行うことで、成功に導くことができます。また、知識が現場で活かされるよう伴走支援を行うことで、データサイエンティストとしての成長が現場に貢献する形で定着します。
企業にとって価値を生み出すデータサイエンティストを育成するためには、技術的な能力だけでなく、ビジネスの現場を理解し、課題解決に応用できる実践的なスキルが不可欠です。そのためには、現場の声を大切にし、実務に即した学びの機会を設計することが、人材育成成功のカギとなるでしょう。
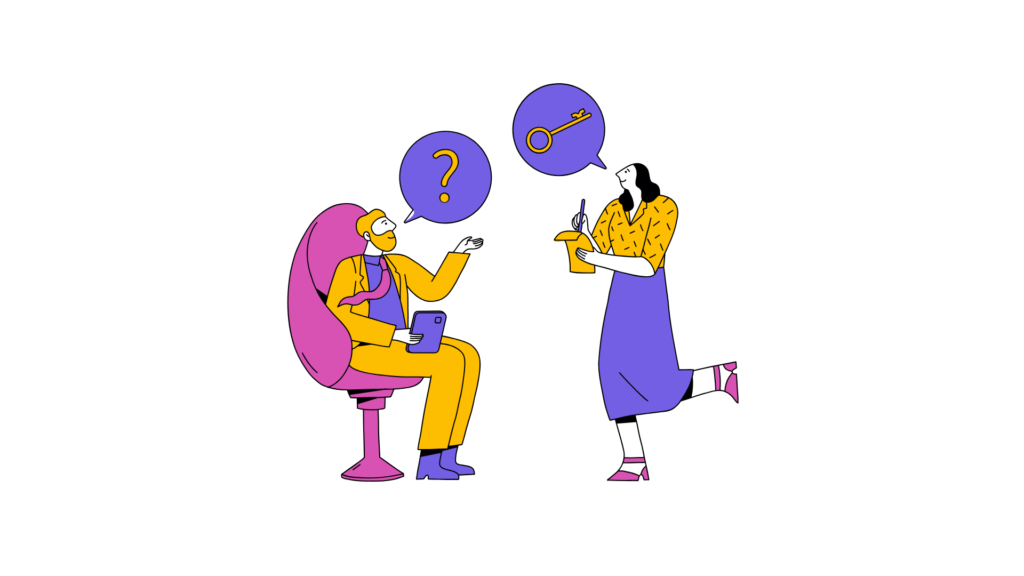
<執筆・監修>アルサーガパートナーズ株式会社 技術ブログ制作チーム

RK
データサイエンティスト。
前職含めデータサイエンス歴14年。
電力、製造小売、航空、通信、医療、製薬、食品製造、飲料メーカーなど、幅広い業界で分析業務・モデル作成を担当。