
Techブログ
Techブログ
この連載では、筆者がこれまで外資系コンサルティングファーム等でデータサイエンティストとして働いてきた経験を踏まえ、価値のあるデータサイエンティストについて記載させていただきます。
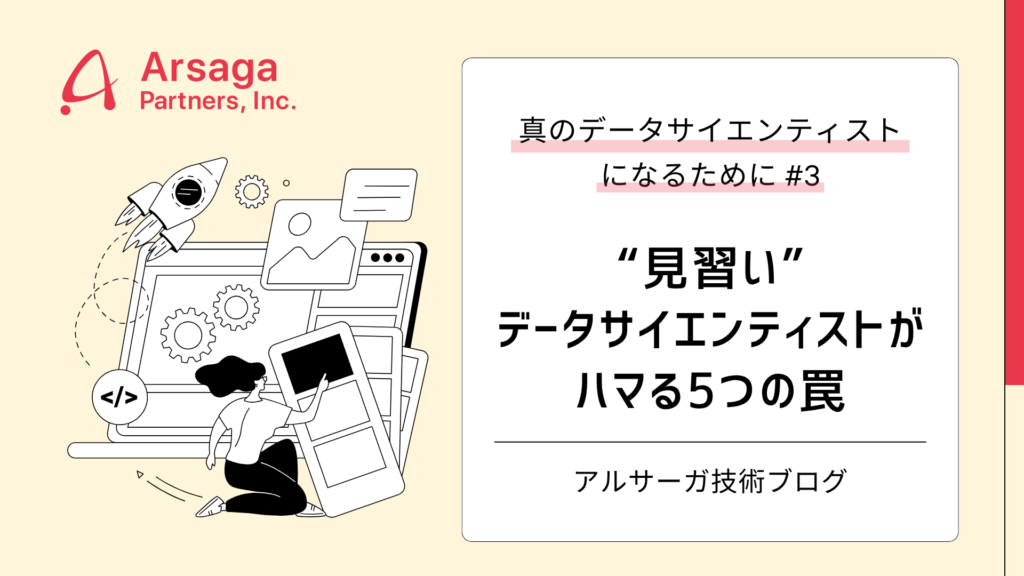
目次
第1回では、“問題だらけのデータサイエンティスト”のリアルな姿を暴き、第2回では“本物”になるためのマインドセットや必須スキルを整理しました。今回の第3回は、その狭間、いわゆる“見習い期” にスポットを当てます。
私自身、外資系ファーム時代に「精度0.89!」と喜んで帰宅し、翌朝クライアントの本番環境で0.25に急降下。冷や汗とともに、あの夜中の胃痛はもう二度と味わいたくない…。と感じました。
そんな苦い経験も踏まえつつ、今回は“見習い”データサイエンティストが陥りがちな5つの罠と、その回避策を体験談ベースでご紹介します。
関連記事:
【真のデータサイエンティストになるために #1】本当にいた!問題だらけのデータサイエンティスト
【真のデータサイエンティストになるために #2】本物のデータサイエンティストになるために必要なマインドセット・知識・経験とは?
学習時点では驚異の精度。ところが本番投入した途端、外した予測でカスタマーサクセス(CS)が大炎上。原因をたどると、「納品予定日」や「最新実績」が説明変数に混入していた。これが典型的なリークです。
たとえば、通信会社の顧客維持の案件で解約予測モデルを作成していたときのこと。隣のチームが解約実績データの「解約年」をカテゴリー変換し、予測を算出していました。予測対象の年が変わるまで誰も気づかず、ある日突然エラーが発生。学習・テストデータには存在しなかった来年のデータが原因で本番でエラーに。その原因を調べてほしいと筆者に依頼が届いたことがありました。
有効な対策例:
・リークチェックシートをGoogleスプレッドシートで全員と共有
・Forward-Chaining CV(時系列を守る検証法※2)をプロジェクトの標準に設定
・「テスト精度が良すぎたらリークや過学習を疑う」という文化をチーム内でつくる
※1.リーク(データリーク):モデルの学習に未来の情報や本来使ってはいけない情報が混入し、過剰に良い結果が出てしまう現象。実際の運用では性能が激減する原因となる。
※2.Forward-Chaining CV(時系列交差検証):時系列データの未来情報漏れを防ぐ検証方法。過去から未来に向けてモデルの汎用性を確認する。

「LightGBM(※3)がうまくやってくれるはず」とEDA(探索的データ分析※4)を省くと、欠損だらけのカラムや外れ値がそのまま学習に流れ込み、チューニング沼へ突入します。
かつて広告クリック率の予測で、ユーザーIDが特徴量に入っていることに終盤まで気づかず、モデルがユーザーIDを「重要特徴量」と誤認。よって、試行時間とGPU(※5)コストをかなり溶かしてしまいました。
有効な対策例:
・プロジェクト開始1日目に“5分EDAスクリプト”を全員で走らせる
・Pull Request(※6)の最初にdf.describe()(※7)と欠損ヒートマップを貼る運用をルール化
・基礎集計終了時にレビューを徹底する
※3.LightGBM:Microsoftが開発した高速で高性能な勾配ブースティング決定木の機械学習ライブラリ。大量データの処理に強い。
※4.EDA(探索的データ分析):データの特徴や欠損、外れ値などを把握する初期段階の分析。ここを飛ばすと後々のモデル精度やコストに悪影響が出る。
※5.GPU(グラフィックス処理装置):並列計算に優れ、機械学習の高速処理に使われる専用ハードウェア。
※6.Pull Request:ソフトウェア開発におけるコード変更提案のこと。レビューや議論を経てメインコードへマージされる。
※7.df.describe():PandasのDataFrameで使うメソッド。数値データの基本的な統計量(平均、標準偏差、最小値、最大値、四分位数など)を一括で表示し、データの概要を把握するのに役立つ。
お客様は「週次で大まかな増減理由が分かる可視化」を望んでいるのに、見習いはBERTやGPT-3でテキスト分類を提案。結果、納期も工数も合わず、プロジェクトは“壮大なPoC(※8)”に化けます。
有効な対策例:
・「目的、制約、コスト、期日」を明確にする
・翌営業日に意思決定に使えるチャートを1枚添えて信頼を掴む
・モデル高度化は「ROIシミュレーション→小さく試す→効果確認」の三段階で行う
※8.PoC(Proof of Concept):技術的な実現可能性や価値を検証するための試験的プロジェクト。完成品ではなく実験的な段階を指す。
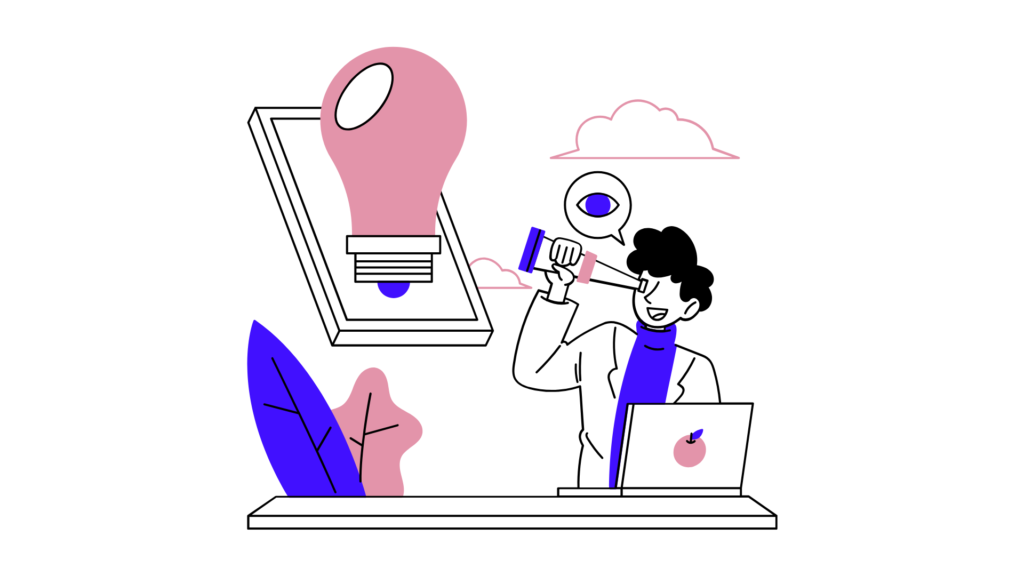
「集中しているから」とレビューを後回しにし、気づけば方向違いのモデルを48時間ぶっ続けで学習してしまったらクラウド請求書は月末に爆発、ということが発生します。
有効な対策例:
・週2×30分の「ライトレビュー」をカレンダーに固定
・分析設計時にお客様の求めることを再確認
計算リソースを無限に使い、会議を増やし、結局プロジェクト単価を押し上げる。新人は「学習=タダ」と錯覚しがち。
有効な対策例:
・請求の来ない人件費にも気を配る
・Auto-Shutdown(※9)の活用と、Terraform(※10)による強制タグでVM(Virtual Machine※11)の停止忘れを防ぐ(クラウド費用対策)
・KPIに意思決定リードタイムを含め、結果待ちによる商機逸失対策
※9.Auto-Shutdown:クラウド上の仮想マシンなどを自動的に停止する仕組み。使いっぱなしによる無駄なコストを防ぐために利用される。
※10.Terraform:クラウドリソースの構築や管理をコードで自動化するツール。設定をコードとして記述し、インフラの再現性や変更管理を効率化する。
※11.VM(Virtual Machine):物理的なコンピュータ上で動作する仮想的なコンピュータ環境。複数のVMを1台の物理マシンで動かせるため、効率的なリソース利用が可能。
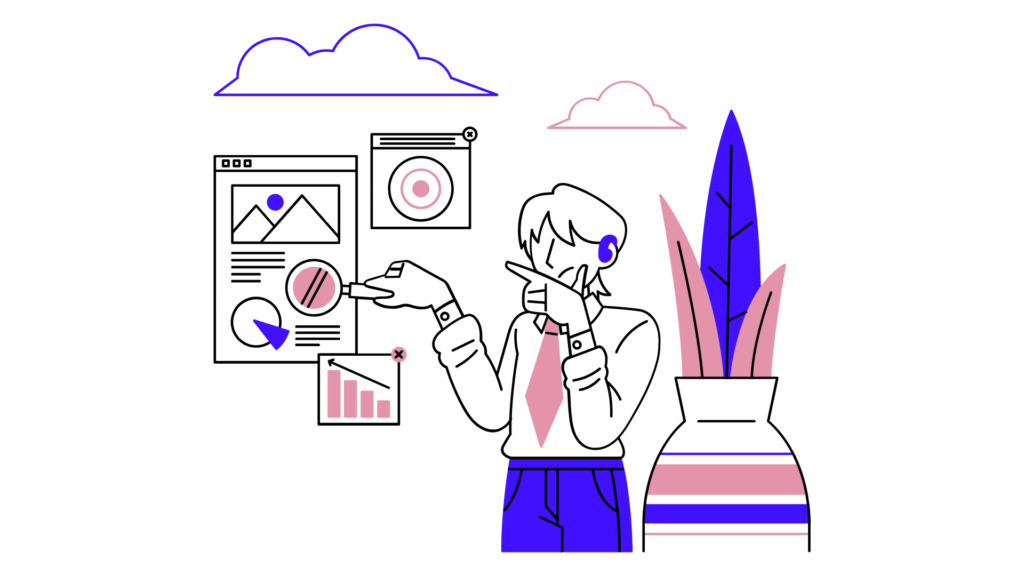
“見習い”データサイエンティストが陥る5つの罠。それは、スキルの未熟さではなく、チーム文化とプロセスの欠如によって引き起こされるものがほとんどです。
モデルの精度や複雑さに目を奪われるあまり、「誰のために」「何の目的で」データ分析をしているのかという視点が抜け落ちると、プロジェクトは簡単に迷走します。だからこそ必要なのは、属人的な技量ではなく、チームでの予防策の仕組み化です。
・「リークは起こる前提」でのチェック体制
・「まず5分EDA」から始める文化
・「1チャートで信頼を掴む」意識づけ
・「レビューの強制実施」と「GPU利用の見える化」
・「自分の時給を意識する」コスト感覚の教育
こうした“文化”と“プロセス”を徹底することで、罠は個人の責任ではなく組織で潰せる課題に変わります。華やかなモデル構築の裏で、泥臭く地味な“予防”と“調整”を積み重ねる。その地道な努力の先に、真に価値あるデータサイエンティストが育つのです。

第4回は”見習い”データサイエンティストから“独り立ち”するために必要な、これまでに焦点を当ててこなかったスキルや考え方を紹介します。机上の知識やツール習得だけでは埋まらない、“現場で頼られる人”になるためのヒントをお届け。
次回もぜひご期待ください!
<執筆・監修>
アルサーガパートナーズ株式会社 技術ブログ制作チーム

RK
データサイエンティスト。
前職含めデータサイエンス歴14年。
電力、製造小売、航空、通信、医療、製薬、食品製造、飲料メーカーなど、幅広い業界で分析業務・モデル作成を担当。