
DXコラム
DXコラム

生成AIという言葉を、教育関係者の方々が耳にする機会も増えてきたのではないでしょうか。ここ数年で急速に注目を集めているこの技術は、教育現場にも確実に広がりつつあります。
たとえば、教材の作成や生徒一人ひとりに合わせた学習アドバイスの提供など、これまで人手に頼っていた教育活動。これらが、生成AIの力を借りることでより効率的かつ柔軟に行えるようになってきました。
一方で、生成AIを導入すればすぐに効果が出るとは限りません。現場での活用が進まない背景には、さまざまなハードルや誤解も存在しています。
この記事では、教育分野における生成AIの仕組みや活用事例、導入時に注意すべきポイントまで、具体的な内容を交えて分かりやすく解説していきます。あわせて、アルサーガパートナーズが開発した教育向け生成AIサービス「AI+Me(アイミー)」や、現場のリアルな声が反映された調査リリースもご紹介します。
これから教育現場で生成AIの導入を検討している方にとって、実践的なヒントが得られる内容となっています。ぜひ最後までお読みください。
目次

生成AIとは、テキスト・画像・音声など、さまざまな形式のコンテンツを自動で生成する人工知能のことを指します。たとえばChatGPTのように、人間と対話する形で自然な文章を作るAIも、代表的な生成AIの一つです。
この技術は、過去に学習した膨大なデータをもとに「次に来るべき言葉」や「適切な表現」を予測して出力しています。つまり、ルールベースではなく、統計的な学習によって人間らしい文章や内容を作り出しているのです。
従来のAIと異なり、生成AIは「与えられた入力に対して何かを創り出す」能力に優れており、応用範囲も非常に広いのが特徴です。
教育分野において生成AIが注目を集めている背景には、いくつかの社会的な変化があります。
まず一つは、少子化に伴う教員不足の問題です。教員一人ひとりの負担が大きくなる中で、作業の一部を生成AIが補うことは、業務の効率化に直結します。
次に、GIGAスクール構想などによる教育現場のICT化が進み、デジタルツールを前提とした学びの環境が整備されつつあります。そうした中で、生成AIを使った教育支援の導入は、より現実的な選択肢となってきました。
さらに、子どもたちの学習スタイルが多様化するなかで、個別最適化された学びを実現する手段としても、生成AIは大きな可能性を秘めています。一人ひとりの理解度や興味に合わせて学習内容を変えることができれば、学びの質そのものが大きく変わってくるでしょう。

まず注目されているのが、教員による教材作成や授業の計画立案といった準備作業における活用です。
たとえば、生成AIに「中学2年生向けの理科のテスト問題を作って」と指示するだけで、問題文と選択肢、さらには解説まで生成してくれます。これにより、これまで数時間かかっていた教材づくりが、わずか数分で完了することも。
もちろん、生成AIが出力した内容をそのまま使うのではなく、教員がチェックして手を加える必要はありますが、「ゼロから考える」時間が大幅に削減される点は大きなメリットです。
生徒側の学びにも、生成AIは大きな可能性をもたらします。
たとえば、ある生徒が「英語の文法が苦手」と感じている場合、生成AIがその生徒のレベルや理解度に応じた練習問題を作成し、わかりやすい解説も添えてくれる仕組みが導入されています。
さらに、授業中に理解が追いつかなかったポイントを、自宅で生成AIに質問することで補うことも可能です。人目を気にせず、自分のペースで何度でも質問できる環境は、生徒の学習意欲の向上にもつながっています。
教員が抱える業務の中には、採点・コメント記入・資料整理といった時間のかかる作業が多く存在します。こうした業務の一部にも生成AIが導入され始めています。
実際に、アルサーガパートナーズが全国の教職員向けに行った調査によると、「教材作成の時間短縮になった」「授業準備の負担削減になった」といった前向きな意見が確認されています。
出典調査リリース:【生成AI活用実態調査|教育業編】「AIで業務がラクになった」教員は3割未満。 便利なはずのAIが新たな業務を生む側面も

生成AIの導入によって、「教員が一方的に教える」という従来の授業スタイルにも変化が見られはじめています。
生成AIが答えを提示してくれる環境では、生徒が自ら課題を見つけ、調べ、考え、生成AIと対話しながら学びを深めていくスタイルが育ちつつあります。これは「探究型学習」とも相性が良く、生徒の主体性を育む上で大きな可能性を秘めています。
これにより、教員は知識を一方的に伝える立場から、「生徒の学びを導くファシリテーター」へと役割をシフトしていくことも求められるようになるかもしれません。

生成AIを教育現場に導入する際、まず最初に確認すべきなのは「安全性」と「実用性」です。
特に気をつけたいのがデータの取り扱いです。生成AIを活用する際は生徒の学習履歴や個人情報に関するデータを扱う場面があるため、情報漏洩のリスクを最小限に抑える仕組みが求められます。クラウド型生成AIの場合は、どのサーバーにデータが保管されるか、外部との連携がどうなっているかを事前に把握しておくと安心です。
また、操作性も重要なポイントです。生成AIに不慣れな教員や事務スタッフが現場には多いため、直感的に使えるUI(操作画面)であるかどうか、導入前に実際に触れる機会を設けると良いでしょう。
そして何より大切なのが「現場の声を反映すること」です。システムを導入する側と使う側に温度差があると、せっかくのツールも活用されなくなってしまいます。
生成AIに期待はあっても、実際の活用が進まないケースも少なくありません。
アルサーガパートナーズが実施した調査でも、「生成AIを導入したが、業務の負担が軽減されていない」と回答した教員は、約4割にのぼりました。これは、導入したシステムが現場のニーズに合っていなかったり、使いこなせなかったりすることが原因としてあるでしょう。
対策としては、段階的な導入と研修が効果的です。最初から全ての教職員に利用を求めるのではなく、まずは一部の教員が先行して活用し、成果や課題を共有することで現場導入への不安を軽減できます。
また、生成AIに対する誤解を解くことも大切です。「AIに仕事を奪われる」という不安ではなく、「AIを使うことで人間にしかできない仕事に集中できる」という意識の転換が必要です。
生成AIはあくまでも「補助的な存在」であることを意識しながら活用することが、効果を最大化するための鍵です。
たとえば、日常の業務に少しずつ組み込んでいくことで、徐々に教員の作業効率を高め、教育の質そのものを引き上げていくことが可能になります。
アルサーガパートナーズが提供する教育向け生成AI支援サービス「AI+Me」では、教育機関ごとのニーズに応じた導入支援が行われており、現場の声を反映したシステムとなっています。導入後のサポート体制も充実しており、技術面の支援だけでなく、実践に即した研修や相談も可能です。
関連プレスリリース:アルサーガパートナーズ、先生や児童・生徒の声から生まれた 教育向け生成AIサービス「AI+Me(アイミー)」を本格展開
学校ごとに必要な機能や方針は異なるため、導入に際しては「現場と一緒につくる」という視点を持つことが、成功のカギを握ります。
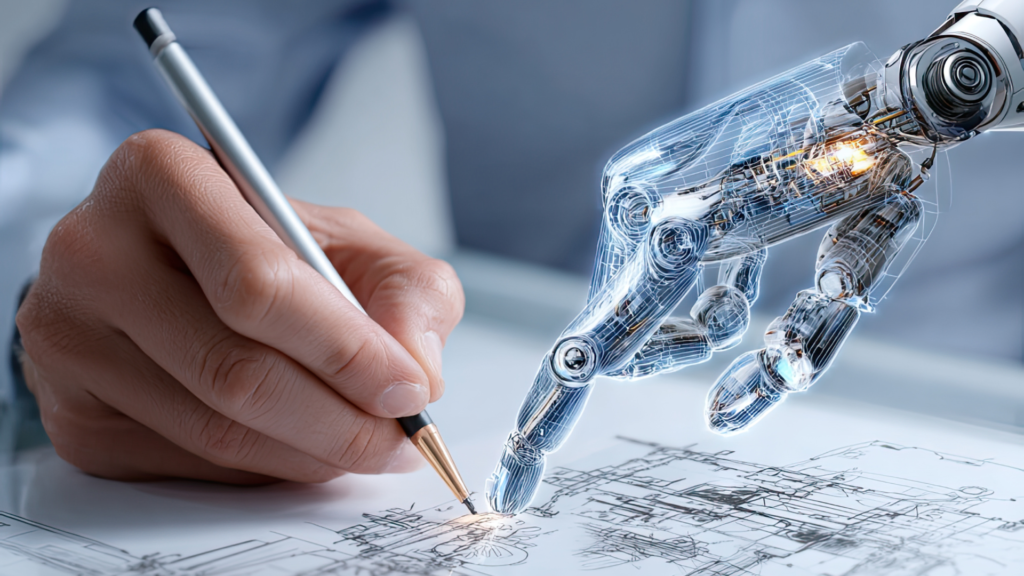
生成AIが教育現場にもたらすインパクトは、今後ますます大きくなっていくと考えられます。
これまで教員が担っていた業務の一部を生成AIが代替することで、教員は「教える」ことから「伴走する」役割へと変化していくかもしれません。また、生徒一人ひとりが自分のペースで学び、生成AIと対話を通して理解を深めていく学習スタイルが定着すれば、教育のあり方そのものが大きく変わっていくでしょう。
とはいえ、進化した技術をただ取り入れるのではなく、教育の目的を見失わない姿勢が何より大切です。生成AIはあくまでも「学びを支える道具」であり、その使い方次第で良くも悪くもなる可能性があります。
改めて、教育現場に生成AIを導入する際に押さえておきたい3つのポイントをまとめます。
・安全性と操作性を確認し、現場の不安を解消する
・一部導入からはじめ、段階的に広げる運用を検討する
・生成AIを「使いこなす」ための意識づけと研修を取り入れる
今後も、こうした動きが加速する中で、生成AIと教育の関係はより深まり、多様な学びの形が広がっていくことでしょう。
導入支援サービス「AI+Me」や、実際の調査結果を参考にしながら、自校に合ったAI活用の方法を探ってみてはいかがでしょうか。
(文=広報室 白石)
関連記事:
関連プレスリリース:
【生成AI活用実態調査|教育業編】「AIで業務がラクになった」教員は3割未満。 便利なはずのAIが新たな業務を生む側面も